パリ女性とは違う日本の「性器周りケア」事情 60歳女性は、なぜ脱毛を決めたのか
一方で、ヘアの色が薄くて細い北欧系の方や、肌の色が濃いアフリカ系の人の場合は、機械での判別が難しく、効果的でないというか、施術結果にムラが出やすいといわれます。これが、日本人の場合に白髪が多く混じる前の60歳前後に全脱毛をされる人が増えている理由だと思われます。最近では白髪、産毛対応のものも出始めたようですが、思い立ったら早い方がよいと言うことでしょう。
わたくしの関わっている美容クリニックによると、この60歳前後の女性の脱毛処置は10人に2〜3人くらいの割合だそうです。パリのマダムの場合でしたら、「新しい恋人の趣向?」などと憶測しがちですが、日本女性は全く理由が違うのです。
「他人様に少しでも迷惑にならないように・・・」
聞くところによると、「齢を重ねれば、何から何まで他人様の手を煩わせることになりかねない。その時に少しでもご迷惑にならないようにしたい」とのこと。確かに、介護でシモの世話をもしていただくこととなれば、世話をする側もされる側も、毛はない方が衛生的であり容易であるに決まっています。生れたときの姿に戻る、これもまた“終活”の一つかも知れません。
初めてその話を聞いた時には、少なからずのパリのマダムが自分の性的魅力アップのためにするUHケアであるのに、日本人女性の場合は、なんと切なく寂しい情景なのか、と悲しくなりました。ところが、じっくり調べてみると、どうもそうではないのです。これは美意識。しかも、「終わりを美しくする」だけではない、遺された人たちに「これは参ったな」と思わせる美学なのです。きわめてセンシュアルな、日本人ならではの“粋”だと感じました。そして、ある情景が脳裏をよぎりました。
紅絹裏(もみうら)という語、ご存じですか? 紅絹(もみ)は緋紅色の絹織物のこと。もとは下染めに鬱金(うこん)をつかい紅花(べにばな)で染めました。江戸期から男女を問わず着物の裏地に――こと胴裏や袖裏に――よく用いられ、紅絹裏という慣用語が出来ました。
かつて粋であったものは、使い方次第で野暮にもなりますから難しいのです。だけれど、レトロであるからこそ、キモノなればこその、目に飛び込んでくるショッキング・スカーレット。わたくしは、その鮮やかさにドキリとします。
紅絹裏は文学作品にもよく現れます。夏目漱石は、自伝的小説『硝子戸の中』で、母が若いころ御殿への奉公に上がっていた面影を、蔵の中に見つけた、紅絹裏をつけた着物表の桜や梅が染め出された金糸銀糸の裲襠(かいどり)に想像します。漱石の作品世界において、原色の綾なす場面は珍しく記憶に残ります。
菊池寛は、短編小説『大島が出来る話』で、主人公の譲吉と学生時分世話になった近藤夫人との関係を鮮やかにすくい取って表現します。ある日、近藤夫人は突然死に、譲吉は大きな虚無感を抱えます。そして、形見としてもたらされた大島紬。
と、譲吉の心理を抉り出すのです。愛惜だけではない、年上の女性への敬慕が限りなく恋慕を触発する一瞬ながら、すでに幽明境を異とする身である現実の悲嘆。してやられたような、だからこそ美しく去ってしまわれた残像。泥大島の紅絹裏ひとつの粋といっていいでしょう。UH&DZの全脱毛と紅絹裏。日本の60歳もなかなかのものです。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

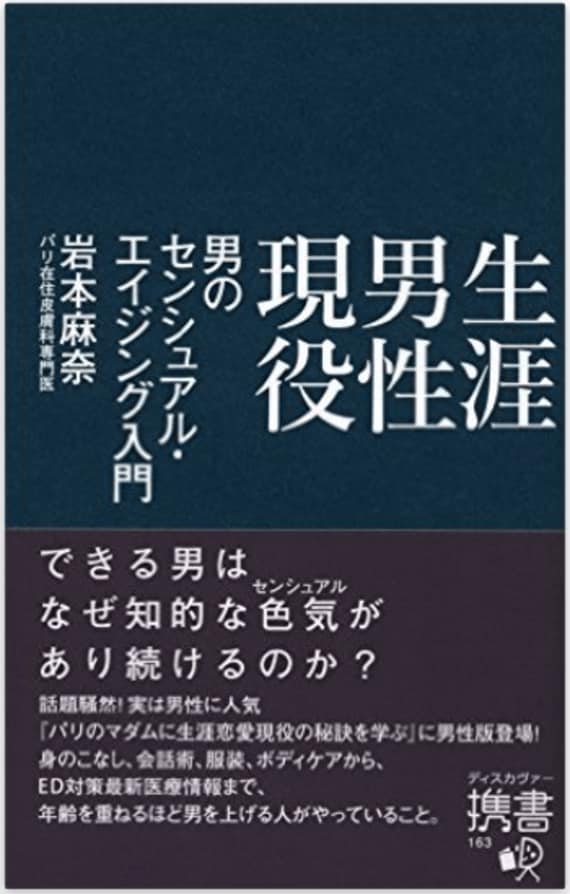
































無料会員登録はこちら
ログインはこちら