薄熙来は市場の自由化(実質的な資本主義化)を進める胡錦濤路線に批判的で、自由を規制してでも平等な社会の建設をめざした毛時代への回帰を標榜し、当時の歌唱を重慶市民に広めるなどの政策を採っていた。すわ文化大革命の再来か、中国動乱も間近か、と日本の一部メディアが色めきたったのも無理はない。
意外に中国に似た戦前日本の「民主化」
しかし現代中国ではなく日本近代史が専門の私は、切迫する危機感というよりも不思議な懐かしさをもってこのニュースを見ていた。なんと悠長な、とお叱りを受けるかもしれないが、悠長なことだけが長い時間軸でものごとを考える歴史屋の取り柄だからしかたない。
そもそも政府の「弱腰外交」を突き上げる形で民主化を要求するのは、明治時代には日本の民権運動家のお家芸で、これを「対外硬」という。
「現政権よりもっと愛国的」な政策の実現を迫るという形の運動であれば、政府の側も取り締まりにくいからで、いわば元祖「愛国無罪」だ。
日露戦争後の1905年、賠償金なしのポーツマス講和に激昂した群衆が起こした日比谷焼き打ち事件もその一例で、こうなると暴徒化の度合いでも、明治の日本人は今日のわれわれよりは、むしろ中国人のほうに近そうな気質である。
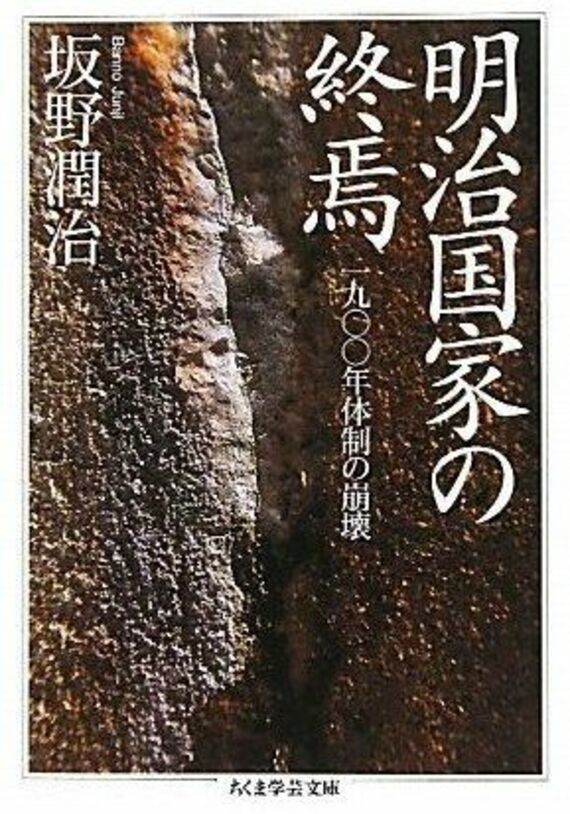
大正に入っても桂太郎内閣を倒した第一次護憲運動(1913年)、続く山本権兵衛内閣を追い詰めたシーメンス事件(1914年)のたびに民衆は帝国議会をとりまき、偏向しているとみなされた新聞社は焼き打ちにあった。
胡錦濤に比して必ずしも薄熙来が真に清廉な庶民派だったわけでもなかろうが、前者でも桂と対立した政友会、後者では倒閣の舞台となった貴族院という本来、都市部の民衆には最も縁遠い守旧派勢力が「正義の味方」扱いで担がれたとは皮肉な話だ……とは、坂野潤治氏の古典『大正政変 1900年体制の崩壊』にみえる挿話だ。
同書は現在、藩閥と政友会との密室の妥協によって安定していた『明治国家の終焉』という、新たなタイトルで文庫に入っているが、おそらく今日の中国も、共産党がかつてのように完全に民意を抑え込めなくなってきているという意味では、「共産国家の終焉」の局面に迫りつつあるように見える。































無料会員登録はこちら
ログインはこちら