脳卒中からの回復は脳画像の読解力で決まる 適切なリハビリを行うために必要なこと
「脳画像を読影できなくても、患者の機能障害と残存機能が適切に評価できているのであれば何ら問題はない」という意見もある。一定程度はそのとおりかもしれない。ただし、どこまで回復する可能性があるかの残存機能を評価することは、脳損傷の程度を脳画像で読影することが科学的基盤になるのは言うまでもない。
そして、多くの患者と異なる脳領域に病巣を持ち、典型的ではない症状を呈している患者の場合はそうはいかない。脳画像から病巣を読み取って生じうる機能障害を推測できずに患者の機能障害や残存機能を見逃したり、障害の解釈ができずに「高次脳機能障害」の一言で片づけてしまったりすることになる。
「脳画像所見と患者の症状は一致しないので、脳画像は患者の障害を理解することに役立たない」という意見もある。確かに画像の所見と患者の症状は「完全」には一致しないものの、脳の損傷状況が患者の症状を規定する重要な要因であることは間違いない。
脳を得意とする医師だけでなく、理学療法士、作業療法士、看護師、介護士、診療放射線技師、ソーシャルワーカーなども脳解剖と脳画像、脳画像と脳機能の関係を理解すれば、質の高いリハビリは実現できる。患者やその家族の立場で考えても、自分の病態についての理解につながる。
脳の神経回路は使わないと発達しない
動かないと、人間は筋肉も骨も心臓も肺も認知機能も弱り、関節が固まり褥瘡(じょくそう=床ずれ)もでき、寝たきりとなってしまう。一方で、専門的に言うと「脳の可塑性」と呼ばれる性質がある。脳の神経回路は使用すると発達し、使わないと退化するということだ。リハビリによる脳の機能回復はこの可塑性によってもたらされる効果と残存脳機能を最大限に発揮させる効果でなされ、人間回復につながる。
昭和時代、私たち脳卒中の治療にかかわる医師は急性期脳卒中治療の暗黒の時代を経験した。なんと、盲目的な安静臥床による内科的治療が最良の急性期脳卒中治療であると信じられていたのである。その結果、患者の多くが廃用症候群となってしまった。現在、廃用症候群を予防して、人間回復をすすめるスタートがリハビリによる早期離床であることは言うまでもない。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

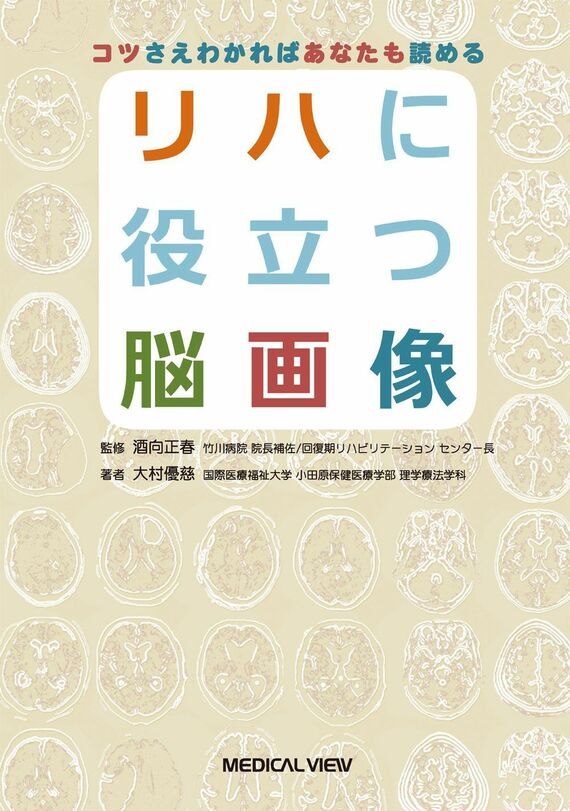






























無料会員登録はこちら
ログインはこちら