創価学会はなぜ社会から嫌われるのか 戦後社会が育てた巨大教団
金(かね)にまつわる恨みほど恐ろしいものはないともいえるが、さらに彼らは、辞めるときに強い引き留め工作を受けたり、辞めてからかつての仲間に誹謗中傷されたりすることもあった。そのため、恨みはさらに増し、内情を暴露したり、池田氏を激しく批判したりして、そうした声が週刊誌に掲載されたりした。
世の中に伝えられる創価学会のイメージは、相当に恐ろしい教団というものであった。そうした時代がかなり長く続くことで、創価学会を嫌う人間が増えていった。
逆に、一般の人間にとって創価学会が存在するメリットは少ない。ただ、会員でなくても選挙の際には公明党に投票する「フレンド票」となれば、友好的に接してくれるし、何か困ったことがあれば公明党の地方議員が相談に乗ってくれたりする。
そうした手段を利用する非会員もいたが、その恩恵にあずからない人間からすれば、それもまた創価学会を嫌う理由になった。外側からは、自分たちの利益だけを追求する極めて利己的な集団に見えたのである。
ただ、こうしたことは、ほとんどが過去のことになった。創価学会が伸びている時代には、多額の金を布教活動に費やす人間が出たが、今はそうした雰囲気はない。多くは、生まれたときから会員になっている信仰2世や3世である。
連立政権入りで安定性が強化された
折伏は影を潜め、新しく会員になるのは、会員の家の赤ん坊ばかりである。聖教新聞には、かつては敵対する勢力や裏切り者を罵倒する言葉があふれていたが、今はそれもない。
公明党が自民党と連立政権を組んでいることも大きい。創価学会は、それを通して、日本社会に安定した地位を築いた。ことさら社会と対立するような状況ではなくなったのである。
週刊誌などが、創価学会にまつわるスキャンダルを暴くこともほとんどなくなった。池田氏も高齢で、その言動が世間をにぎわすこともない。
現在では、一般の日本人が創価学会を嫌わなければならない理由はなくなった。だからこそ、冒頭で述べたように、創価学会の人たちはいい人たちだという声が上がるのである。
しかし、世間から嫌われなくなった創価学会は、宗教教団としての活力を失ったともいえる。会員の伸びは止まり、公明党の得票数も選挙をやるたびに減りつつある。週刊誌が取り上げないのも、記事にしても読者の関心を呼ばないからだ。
はたしてそれが創価学会にとって好ましいことなのか。今、学会の組織はそうしたジレンマに直面している。嫌われてこそ、本来の創価学会なのかもしれないのである。
(「週刊東洋経済」2015年9月26日号を転載)
※本記事を含む週刊東洋経済eビジネス新書「公明党、創価学会よどこへ行く」も発売中です
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

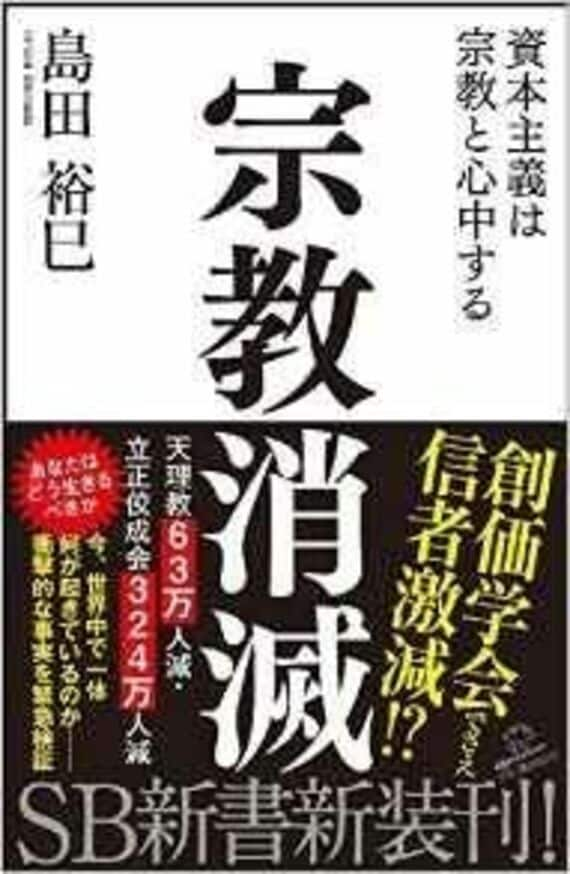































無料会員登録はこちら
ログインはこちら