狂騒の時代に生きたシャネルとローランサンの作品を発表、漫画家・桜沢エリカが語る創作活動と暮らしのバランス
史実をひも解きながら作品を描き進めるうちに、桜沢さんの中でマリー・ローランサンの印象は大きく変わっていったという。
「以前は、ふんわりとしたかわいいイメージでした。でも改めて作品を見てみると、その“かわいい”の中に確かな芯があると感じるようになったんです。あの時代に男性の後ろ盾を必要とせず、全てのものから完全に自立していたことにも驚きましたね。
ローランサンは、いわさきちひろや東郷青児など日本の画家にも影響を与えています。彼女が築いた“かわいい”という表現は時を超え、今の『ちいかわ』までつながっているんじゃないかと思うんです(笑)」
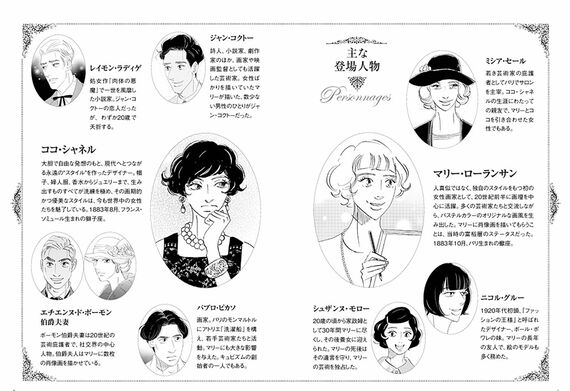
当初はココ・シャネルに強く共感していた桜沢さんだが、創作を進めるうちに自分とローランサンとの共通点を見出すように。
「社交界の華やかな場に出入りしながらも、作品では動物や花など自然のモチーフを好んでいるところが自分に似ていると感じます。私の最初の単行本が『かわいいもの』なので、親近感がありますね」

2人の交流は、シャネルがローランサンに依頼した肖像画の受け取りを拒否したことで、一時的に絶縁状態となった。桜沢さんは、そんな2人の気質を次のように分析する。
「ローランサンは『私の唯一の誇りはパリに生まれたこと』と言うほど、パリ出身であることを自負していました。その反面、地方出身者を小馬鹿にしていたところもあったのかなと思います。肖像画を拒否されたときには、シャネルのことを“田舎娘”と散々に罵っていたそうです」
一方でシャネルは、どこかドライな割り切りがあったのではないかと語る。
「絵が気に入らなかったとしても、親しい友人が描いてくれたのなら普通は受け取りますよね(笑)。あるいは受け取らなくても代金は支払うと思います。シャネルにとっては何よりも仕事が第一で、それ以外のことには一線を引いていたのかもしれません」
桜沢さん自身は、同世代の漫画家から刺激を受けた経験はあったのだろうか。
「岡崎京子さんとは同じ年で、デビューもほぼ同時期でした。仲は良かったけれど、京子ちゃんのことは“天才”だと思っていました。同級生の漫画家には望月ミネタロウさんもいて、当時も、そして今も憧れの存在です」
漫画家を続けるための、2つの原動力
1983年のデビュー以来、第一線で活躍を続ける桜沢エリカさん。創作の原動力の1つは「好奇心を持ち続けること」だという。
「時間があれば美術展に出掛けたり、気になるものを調べたり、どこにアイデアのヒントがあるか分からないので、なるべくいろいろなことに興味を持つようにしています。描きたいと思えるものがないと難しいですし、何より大切なのは“とにかく描き続けること”ですね」
そう語る一方で、描き続けることができなくなった時期もあった。
「30歳くらいのときにひどい失恋をして、『もう描けません』とお休みをいただいたことがありました。朝起きて髪を巻いて、シャネルで散財して、美味しいものを食べに行って……そんなふうに過ごしていたら、2〜3カ月で貯金が無くなってしまったんです。1年は休むつもりが、すぐに働かざるを得なくなりました(笑)」
その頃までは「漫画でお金を稼いでいる」という自覚があまりなかったと振り返る。
「それからは、“お金を稼ぐこと”が純粋な労働意欲になりました。『もう少し描かないと足りないな』と意識することが、今もいい刺激になっていると思います」

































無料会員登録はこちら
ログインはこちら