近年の急激な円安進行…なぜ「安いニッポン」が生まれてしまったのか? 今後の日本が挑むべき「リスクの高い挑戦」とは
日本はいわば「『世界の工場』の、さらにその奥にある工場」へと、その役割を変えつつあるのです。
この転換は、日本の高い技術力を活かす道ではありますが、同時に、ブランド力やプラットフォームを通じて最終消費者を直接支配する、最も収益性の高い市場の主導権を海外企業に明け渡していることを意味します。
下がり続ける食料自給率のリスク
日本の経済構造を議論する上で、最も根源的、かつ見過ごすことのできないリスクが、「食」の安全保障です。
日々の食卓に並ぶ食料の多くを輸入に依存する日本の脆弱性は、ウクライナ侵攻や気候変動といった世界情勢の不安定化を受け、国家の存立に関わる経済安全保障上の最重要課題へと浮上しました。
日本の食料供給基盤の脆弱性は、食料自給率の低さに端的に表れています。
2023年度のカロリーベースの食料自給率は38%にとどまり、国民が消費するエネルギーの6割以上を海外に頼っているのが現実です。
この危機的状況に対し、政府は25年4月、新たな「食料・農業・農村基本計画」を策定し、30年度までに自給率を45%に引き上げるという、極めて野心的な目標を掲げました。
その戦略の中で最も注目すべきは、「輸出促進」を食料安全保障の柱に据えた点です。これは一見、矛盾しているように見えるかもしれません。
しかし、その狙いは、国内の農業を厳しい国際競争の舞台に立たせることで生産性を向上させ、国内の農業基盤そのものを強靭化することにあります。
「海外で稼げる強い農業に育てることこそが、有事の際に国民を養うことができる持続可能な農業につながる」という新たな発想の転換です。この壮大な国家戦略は、日本の農業の未来、ひいては国民の生存そのものを賭けた、リスクの高い挑戦と言えるでしょう。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

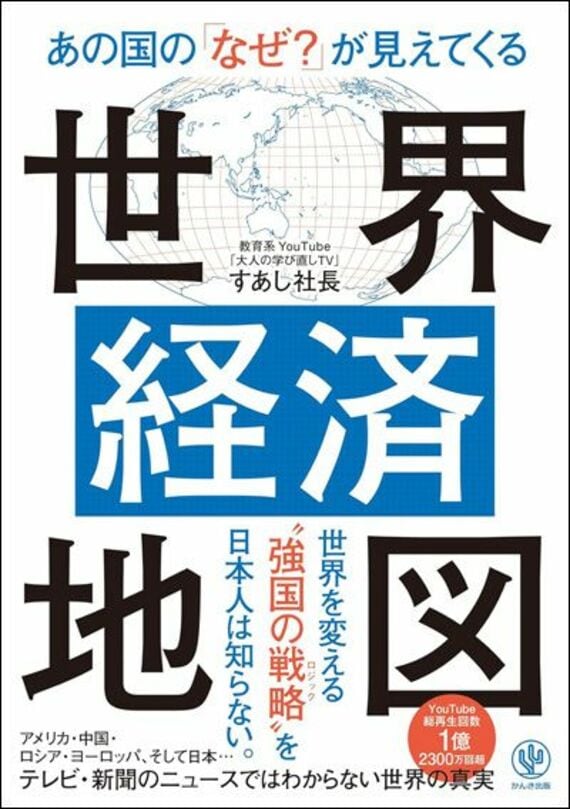






























無料会員登録はこちら
ログインはこちら