熊本は「第二の台湾」になるのか? TSMC進出が招いた"豊富な水"が枯渇する日
今後は生成AIやクラウド処理の需要拡大を背景に、2030年までに累積で約89万ラック分のデータセンターが建設される見通しで、その7割以上はハイパースケール型であると予想されています。これらの施設は、大量の電力を消費するだけでなく、現状では冷却のために大量の水を使用するという特徴を持っています。
冷却方式には空冷式や液冷式などいくつかのバリエーションがありますが、とくに水冷式では、1メガワットあたり年間約2万5000~3万5000立方メートルの水が必要とされることがあり、これは約100世帯の年間水使用量に匹敵します。こうした事情から、水が豊富な地域にデータセンターが集中する傾向が強まっているのです。
地下水の取水「もっと議論がなされるべき」
しかしその一方で、地下水の取水が地域の水循環や生態系に与える影響について、十分な議論がなされているとは言い難いのが現状です。
東京都昭島市は、東京都で唯一、深層地下水を100%公共水道の水源とする自治体です。ここで、日本最大規模の物流・データセンター開発を進めるにあたり、市民からは大量の取水が、地下水や既存井戸や湧水に影響するのではとの懸念が示されました。
市議会や市民団体も説明や環境評価を求めており、対象は水量だけでなく、冷却後の排水の温度や成分、騒音、交通量、景観の変化など複合的な範囲に及んでいます。
千葉県印西市は、すでに約30棟のデータセンターが集積し、「データセンター銀座」とも呼ばれています。ここでは、冷却後の温排水や排熱が周辺環境に与える影響が懸念されており、とくにホタルや湿地の植物など、地域の生態系への影響が問題視されています。
市議会では、市民からの意見を受けて環境影響評価や温排水の監視体制強化を求める動きが出ています。
データセンターは現代社会の情報インフラを支える重要な存在ですが、地域の水資源や自然環境とのバランスをいかに維持し、住民との対話を重ねられるかは、今後ますます重要になります。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

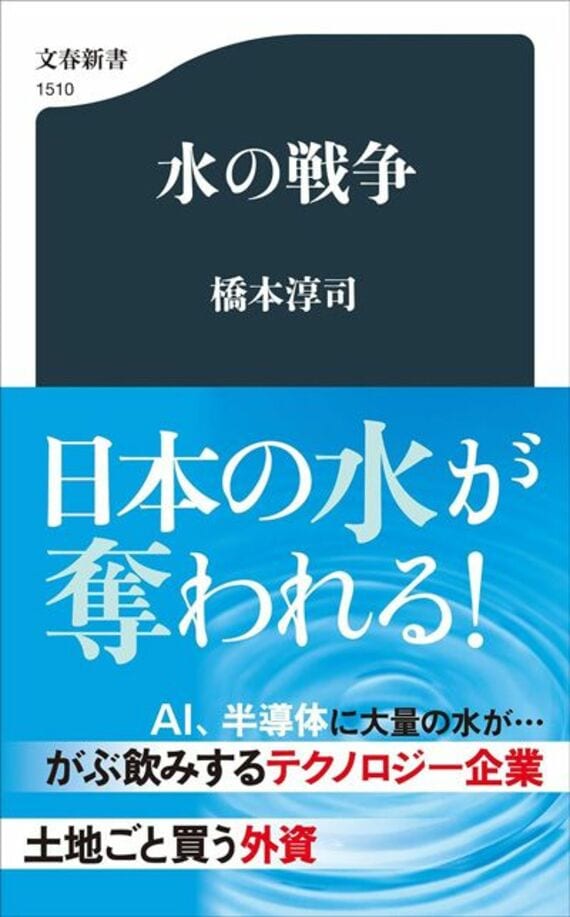
































無料会員登録はこちら
ログインはこちら