やる気があっても成績が上がらない子の盲点 「勉強時間が足りない」以外の令和らしい理由とは
言うまでもないことですが、英単語は一対一で対応する「唯一の正解」があるわけではありません。「suggest」は「提案する」と訳されることが多いですが、文脈によっては「お願いする」「それとなく言う」「ほのめかす」など、微妙に異なるニュアンスが含まれることがあります。
しかし、英単語帳に載っていない表現・つまりは「答え」と定義されていないものがすべて不正解とされてしまうことで、生徒の柔軟な発想・もっと言えば「考える力」が削がれてしまっているのだと思います。
そして、僕が「suggestは、『お願いする』『それとなく言う』『ほのめかす』みたいな意味もあるんだよ」というような話をすると、「わかりました! じゃあsuggestのその3つの意味も合わせて覚えますね」と言う生徒も現れました。
もちろんそれだって間違いではないのですが、そういう話ではなく、もっと本質的に、もっと抽象的に、「答え」ではなく「なぜsuggestがお願いするという意味になることがあるのか」を「考える」必要があるわけです。
単語の意味を一語一義で捉えるのではなく、「この文脈でこの単語はどういう役割を果たしているのか」を考える習慣を身につけないといけないのに、こんなに「答え」をガチガチに意識する学習をしていては、成績も上がるわけがないわけですね。
「答え」を覚える勉強が加速している
この話から何を伝えたいかというと、最近の学生たちの勉強は、「答え」が前提になりすぎていて、「答え」を覚える勉強が加速してしまっているということです。
成績の上がらないと嘆く生徒の勉強スタイルを見ていると、やはり「答え」を前提にしていて、「考える」ということをしない勉強をしている場合が多いです。
昔から、「丸暗記の勉強をしても意味がない」という言説はいろんな学校現場や塾・予備校の先生が語っていたことでした。


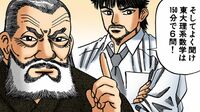




























無料会員登録はこちら
ログインはこちら