やる気があっても成績が上がらない子の盲点 「勉強時間が足りない」以外の令和らしい理由とは
「生徒が最近、ChatGPTを使うことを覚えて、どんな宿題もChatGPTに頼ってしまうんです。英語の宿題を出したら、その英語の問題をChatGPTに日本語に翻訳させて宿題を提出するんですよ。それについて指摘をすると、『え、でもわからない英単語があったら調べていいって、先生だって言ってたじゃないですか!』って大真面目に話すんです」
おそらくその生徒にとっては、勉強や宿題が、「与えられた問題に対して答えを出すこと」なのだと思います。言うまでもなく勉強とは、「答えを出すこと」ではなく、「答えが何かについて悩むこと」、つまりは「考えること」です。
答えを出すことだけに特化した勉強をしていても、勉強の成績は上がりません。だって、先生が「この数学の問題、途中式は言わないが、答えは3だ」とだけ教えてくれたとしても何の意味もないですよね。
ある意味で、勉強においては「答え」なんておまけでしかありません。英語の宿題だってその英語を日本語に直していく過程の中で頭が良くなっていくものであり、ChatGPTが答えを出してくれるからOK、なんて考えるのは間違っています。
“充実”しすぎている最近の参考書
また、最近の参考書を見ていると、重要なポイントにはあらかじめ蛍光ペンで引かれたような線が引いてあることが多いです。「ここ覚えておいてね」というのが明確なのです。
「まとめページ」も充実していて、「覚えるべきこと」があらかじめ用意されているのです。でもその分、逆に生徒は、「なぜこれが大事なのか」を考える時間が減ってしまっています。「線が引かれているポイントさえ覚えればいい」「まとめページがあるから自分で考える必要がない」となってしまうのです。
ある意味でこれも、「答え」を与えられすぎているという話なのだと思います。
勉強とは一体何なのでしょうか。「与えられた問題に対して答えを出す」のが勉強なのであれば、おそらく今後あと10年の間に勉強はいらなくなるでしょう。東大の入試問題であっても、AIが解けるような時代です。
でも、そんな時代だからこそ、「考える勉強」に立ち戻らなければならないのかもしれないと僕は考えています。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら


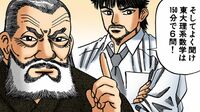




























無料会員登録はこちら
ログインはこちら