心理カウンセラーが説く、上司は部下に「共感」はしても、安易に「同感」してはいけない"納得の理由"
カウンセリングでは共感と同感を次のように表現します。
溺れている人のところへ自分も飛び込んで、一緒に「苦しいね」と溺れるのが、同感してしまうカウンセラー。
溺れている人を岸から眺めて、「かなり苦しいだろうな……」と状況や気持ちを想像するのが、共感するけど同感しないカウンセラー。
誤解してほしくないのですが、他人事のように振る舞うのがカウンセラーということではありません。一緒に溺れてもがいてくれるのも優しさですが、カウンセラーは、溺れている人が自力で岸へ上がるのを支える存在だということです。それが自己解決を促すことになります。
「自己解決できない」習慣をつけかねない
先ほどの例で同感する上司が部下にとってよくないのは、自己解決できない習慣をつけることになるからです。
上司が聞きたいことばかり質問したり、どんどんアドバイスをしたりするようになると、会話の心理的安全性は下がっていくでしょう。
上司主導でものごとが進んでいくので表面的には助かるかもしれませんが、聞かれたこと以外は口を挟む余地がなくなってしまいます。
何か問題が起きると、すぐにいろいろなカウンセラーに相談する「カウンセラーショッピング」に陥っている人がいますが、その原因は誰かがいないと問題を解消できなくなっているからです。自己解決能力の喪失です。
重い話の場合は同感しやすくなることもあるでしょうが、上手な聴き手になりたいなら、共感までに抑えるようにしましょう。相手にとっては、共感で十分なのです。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

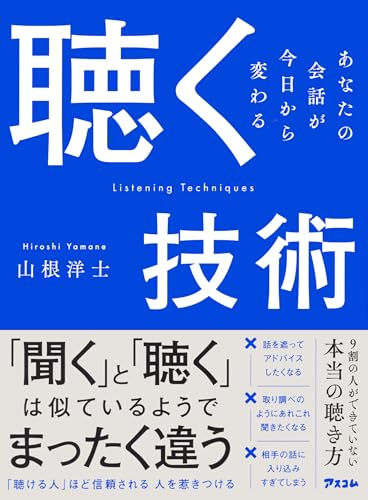






























無料会員登録はこちら
ログインはこちら