「国際的な感覚」「多民族・多言語・多文化の国ならではの広い視野」マレーシア教育移住に希望を抱き渡馬したものの、子どもの学力や生活スタイルでの「マウント合戦」に巻き込まれ、「これでは日本にいる時に苦労した『人間関係』と同じではないか」と悩んでしまう。
そうならないために、親はどんな心構えで渡馬すればよいのでしょうか?

「違い」は気にしないに限る
様々な歴史的背景をもつ多民族・多文化国家のマレーシアには、マレー系および先住民族の経済的地位向上を目的にした優遇策があります。
たとえば不動産購入時、「ブミプトラ割引」というマレー系および先住民族にのみ適用される割引があります。また、国立大学の入学枠も民族によって「違い」があると聞きます。
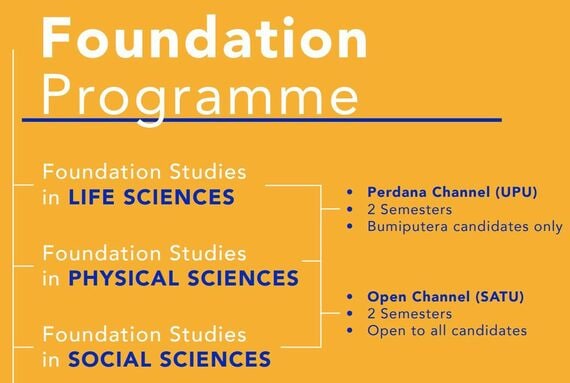
「同じマレーシア人なのに『違い』があるなんて不満に思わないの?」と中華系、インド系の友人に尋ねたらこんな答えが返ってきました。
「今、自分たちがすべきことに集中するほうが建設的だから」
いちいち腹を立てても仕方ない、「違い」は気にしないに限る、と。
隣の芝生と比較して不平不満を言うよりも、自分の芝生を育てることに集中する。もちろん、すべての人がそのような心構えでいるかはわかりませんが、多民族・多文化国家で「違うのが当たり前」のマレーシア人ならではの処世術なのでしょう。
人間関係や文化・価値観の違い等が理由で親自身がマレーシアでの生活に馴染めず、子どもを連れて早期帰国するケースもあると聞きます。
「海外に出た今だからこそ、親御様自身も他人との比較ではなく、自分自身やお子さんに目を向け、『何が自分たちにとって大切にしたい価値なのか』を見つめる良い機会になるのではないでしょうか」(前出・藤井氏)
住み慣れた日本を離れ言語も文化も価値観もまったく違う環境下で生活することは、国際感覚を身につけ視野を広げる好機――それは子どものためだけではなく、私たち親自身が視野を広げ、日本で悩み続けた人間関係のしがらみから卒業するための好機でもあるのかもしれません。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
































無料会員登録はこちら
ログインはこちら