継いだときには50~60軒あった卸売先も、25~26軒に。追い打ちをかけるように、1988年頃から3年連続、取引先のおもちゃ問屋が相次いで夜逃げする。未払金はそれぞれ500万~600万円、合計1500万円以上。当時の年商から考えれば、あまりにも巨額な損失だ。
しかし、中野さんは動じなかった。
「駄菓子製造はお金を借りてまでする商売ちゃう。借りなあかんくなったら、すぐやめろ」
父から継いだときの、たった一つの「申し送り」が、事業の行く末を守り続けていたのだ。
「一銭も借金をしていなかったから、慰安旅行には行けなくなったけど、『堪えたなあ』くらいで済んだんよ」
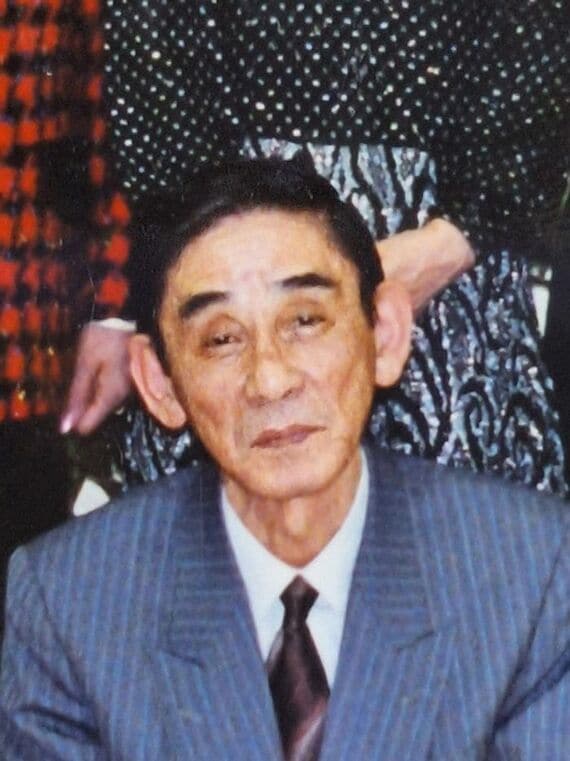
その頃から今まで、売り上げも大きくは下降せず、微弱・微減で推移できている。手を広げすぎずに小さく商売し、原材料の高騰は、卸売先に相談して値上げしてきた。だから、出荷量は減っても利益を確保できているのだ。
一方で、原材料費を最小限に抑えて品質を上げる努力も続けている。ヤッターめんの麺は、最初は麺業者から、形が不揃いの廃棄予定品を安く仕入れていた。そこから転々とし、現在はあるラーメン店から調達している。ただし、この店に決まってからも値上げは続いており、そのたび、卸値も5%ほど上げざるをえない。ヤッターめん発売当初からすると、3〜4倍の仕入れ値になっている。
ヤッターめんが「年中売れる救世主」に
ほかにも課題はあった。社長就任当初はチョコレートが主体だったため、溶けやすい夏、毎年売り上げが3〜4割減っていたのだ。そこで、ゼリーやわらび餅を開発したが、カビが発生し断念。高価な設備機械が無駄になってしまった。ジュースもやってみたが、重たいばかりで儲からない。
しかし、1982年に誕生したヤッターめんが徐々にヒット商品となり、年中売れる救世主となった。































無料会員登録はこちら
ログインはこちら