「どうぞ、おかけください。最近の体調について気になることを自由にお話しください」
少し戸惑いながら、「いや、まあ……なんか熱が出て……」と話し始めると、ロボットが間髪を入れず反応します。
「発熱が主な症状ということですね? ほかにも気になることがあれば教えてください」
さらに、「一番困ってるのは、あさって次女のピアノの発表会があることです。どうしても行きたくて」と続けると、その場で静かにスマホが反応を始めます。患者さん自身のChatGPTアプリが、音声をもとに自動的に情報を整理してまとめるのです。
ChatGPTによる「問診要約」の一例
4日前の夜7時ごろ、急に38.7℃の発熱。休んでも治らず、近所の薬局で買った解熱剤で一時的に下げたが、その後も平均37.7℃前後が続き、今朝からまた上昇傾向。水分摂取量は24時間で750mlと少なめで、お通じは2日間なし。次女のピアノ発表会に出席したいと強く希望。
その後、「吐き気はありますか?」「めまいは?」と、ロボットはスマホを通じて追加の確認を行い、会話の文脈を理解したうえで、情報を構造化し、記録します。
「問診完了しました」と告げられると同時に奥の扉が開き、医師が登場。
「こんにちは。いまの問診内容、拝見しました」とカルテ画面をさっと確認し、そのまま会話に入ります。
この診察室には、患者さん、医師、問診ロボット、そしてChatGPTという「4人の参加者」が存在します。患者さんの言葉にならない不安や、うまく整理できない情報も、AIが橋渡しをしてくれる。そこでは、患者さんが検査データなどをどう扱うかが重要です。
糖尿病や高血圧の患者さんが日々の検査データをひとまず入力し、すべてを医師に説明する代わりにChatGPTに要点を説明してもらったり、医療にまだ慣れないがん患者さんが、プリントアウトを受け取るたびに入力したり。
こうした生成AIの利用は、一般の方が使ってこそ意味があり、うまく活用すれば診療の質を劇的に向上させます。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

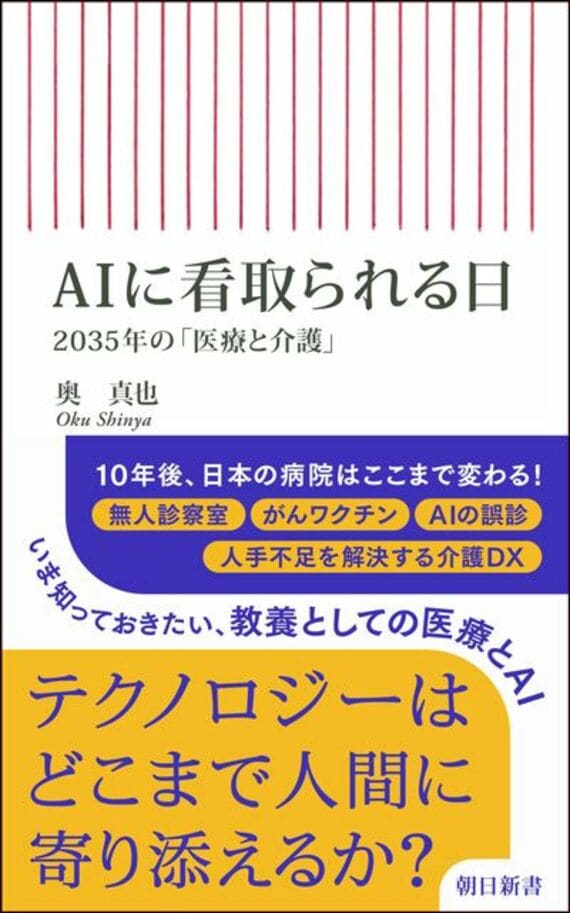


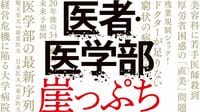



























無料会員登録はこちら
ログインはこちら