さて、このようなヤブ医者的な外科医に出会ってしまう不運も、各ステップで属人的な判断基準に従うのではなく、外科手術がAI画像診断と結びつき、AIが「ここからここまでの範囲を切ってください」と明示した部分だけを切るのであれば、そう簡単には起こらないでしょう。
それが人間医師にとって「楽しい」のかは別として、患者さんにとってはそれでよいのですから。
現代の社会病理として、「ヤブ医者」の意味合いが少しばかり多様化しています。つまり、自分が診ている患者さんに必要のないことはわかっていながら、病院の売上を増やすために余計な薬を処方する経済型「ヤブ医者」の存在です。
しかしAIが診察を主導し、医師が単なる助手にとどまれば、儲けタイプのヤブ医者が無理に保険点数を稼ごうとしても、AI診断との差が悪目立ちし、システム的にはねられてしまうので、急速に駆逐されていくことになります。
AIが変える診察室の風景
現代の医療では、AIの登場以前から「知識の外部化」は始まっていました。かつて名医だけが持っていた職人芸のような暗黙知は、診療ガイドラインという形で外に記録され、医師の判断のばらつきを減らす役割を担っています。
1990年代以降、エビデンスに基づく医療が進み、関連学会が最新の研究成果をもとに治療の手引きを示すようになりました。ガイドラインはいまやウェブで即座に参照でき、診察中に医師がパソコンで確認することさえ珍しくありません。
頭に入っていなければ、診察中に医師がパソコンでさりげなく確認することもあります。
薬の名前や用量も、銀行振込の際に支店名を入力するように、数文字で検索すればすぐに必要な情報が出てくるので、だんだん記憶に頼らなくなってきています。風邪や高血圧といった「よくある病気」では、誰が診ても同じ診断と治療にたどりつける時代ともいえます。
診察室の医師と患者さんとの会話やその記録は、AIによって大きく変わりつつあります。
日本の診療現場でもkanaVoやWarokuなど、診察室の会話をリアルタイムでテキスト化し、要約して電子カルテに自動入力するAIシステムが導入され始めています。



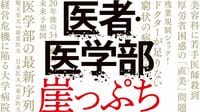



























無料会員登録はこちら
ログインはこちら