今後の対策は?
まず根源的には、どのように店舗側が廃棄ロスを負担するかが問題だ。どう本部側と分担するか。
もちろん勝手にラベルを貼り直す店舗側は悪いのだが、その動機を極力小さくする金銭的ディスインセンティブが必要だろう。また、そもそも余るのが問題ともいえる。より精度の高い需要予測モデルを作って行くことも重要だろう。
つぎに違反者に罰則を設定する。ただ働き手がいなくなったらどうしようもないので、じっくりと教育を重ねるしかないだろう。研修の機会を増やす必要もある。また店舗内で二重のラベルチェックを実施するなどの方法も考えられる。
私はさほど勧めたいわけではないものの、内部通報制度も有効なはずだ。ワンオペで他の従業員がまったく知らなかった可能性もなくはない。ただ、その多くは、他従業員が一度は見聞きしたことがあったはずだ。
また本部の監査体制として抜き打ちのチェックや、技術的な取り組みも求められる。たとえばラベル印字や商品にラベルを貼る際に、不正を検知したり、貼れなくなるなどの工夫だ。
ここまでが短期的な取り組み。さらに中長期的に考慮するならば第三者機関でのチェックや、専門部門を創設することもありだろう(店内調理が同チェーンの付加価値でありつづけるならば)。安全第一の前提を何度も繰り返し点呼し、不正のない風土をつくりあげてほしい。
ところで、当事案をうけて、今後の利用を控えるといった声が散見される。また、差別化商品が販売されないことから、自然と足が遠のく消費者もいるようだ。たまたま真夏に発覚したため、食中毒を想起したひとも多かったのだろう。ぜひ同社には早めの対策発表を望みたいところだ。
なお、不幸中の幸いだったのが、現時点では健康被害が報告されていない点だ。現在、同社ではフリーダイヤルで相談を受け付けている。
ちなみにミニストップは業績が絶好調とはいいがたく、同社の経営戦略を変更する機会となるだろう。同時に、他のコンビニ各社についても店内の品質維持体制の見直しが求められる契機になったはずだ。
ラベルの一枚は、ただの紙切れではなく、企業の信頼そのものだったのだ。ラベルはもしかしてすぐにはがせるかもしれないが、消費者の信頼もすぐにはがれおちる。ぜひ同チェーンには誠実さで、ふたたび信頼を貼り直してほしい。同チェーンの愛好家から申し添えておく。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

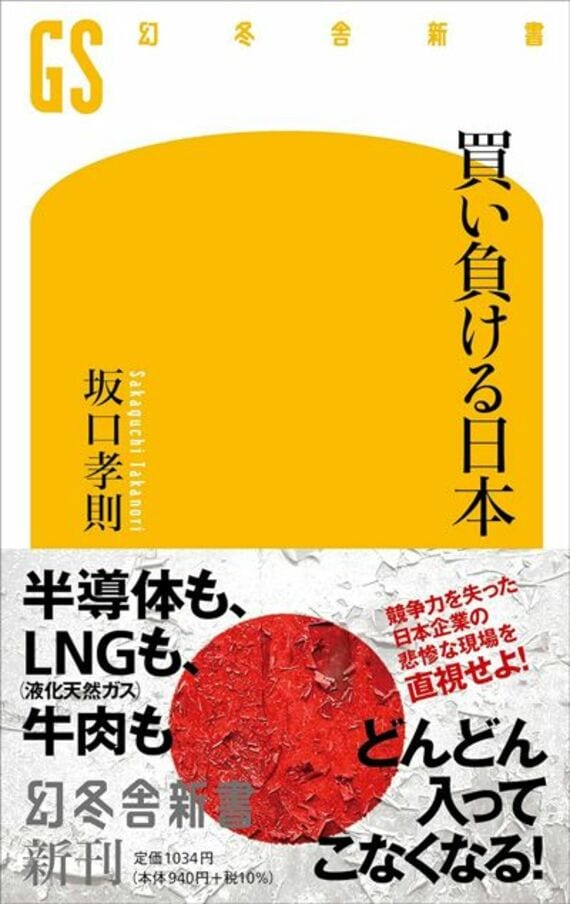






























無料会員登録はこちら
ログインはこちら