大濱のいう「一般の世俗社会における価値観や通念」が及ばない「絶対的世界」が支配していたことはもちろんだが、暴力の正当化に「愛の鞭」という言葉を用いていたことも、前述の軍隊の回想と共通している。政治学者の丸山眞男は、このような極めて凄惨な暴力の上意下達を「抑圧の移譲」と呼んだ(古矢旬編・注『超国家主義の論理と心理 他八篇』岩波文庫)。
「日常生活における上位者からの抑圧を下位者に順次移譲して行くことによって全体のバランスが保持されているような体系」であり、そこにおいては本人の自由な主体的意識は存在せず、自分の行動を制約する良心は機能していない。自分が上の者にされた振る舞いを今度は自分が下の者にするのである。
これがただの組織と異なるのは、激しい運動やトレーニングなどの延長線上で身体に染み込まされる形で「移譲」されることだ。これこそが体罰=暴力の実相といえる。
このような身体性を共有したメンバーは、「苦楽をともにする」の「苦」に、体罰も包摂されてしまうため、その暴力性のインパクトが緩和され、むしろ鈍感になり得る。
閉鎖的な環境が問題を根深くする
しかも、学校という空間そのものが「自己を中心とする絶対的世界」に陥りやすい。ブラック校則などがまさしくそれを体現しているが、ここには一般社会における法律や常識よりも自分たちの“掟”が優越するという確信がある。
そうなると、掟を破った個人に対する度が過ぎた制裁についても許容されることになる。それがSNSを介して初めて暴かれたという経緯が意味するところは大きい。
同様の聖域は、学校だけではなく、さまざまな企業や団体においても生じ得る。家族などの単位も例外ではない。だが、身体性がかかわるようなものは、強い同調性が働きやすく離脱が難しい面がある。
繰り返すが、一般社会で犯罪行為として認識される出来事が総じて不問に付されるのは、これまで紹介してきた私的制裁を正当なものとして捉える信仰共同体を生きているからにほかならない。
わたしたちは今回の不祥事をスポーツ特有の事象とみなしやすいが、ここには日本社会に巣くっている普遍的な問題が露呈していることをもっと認識すべきだろう。

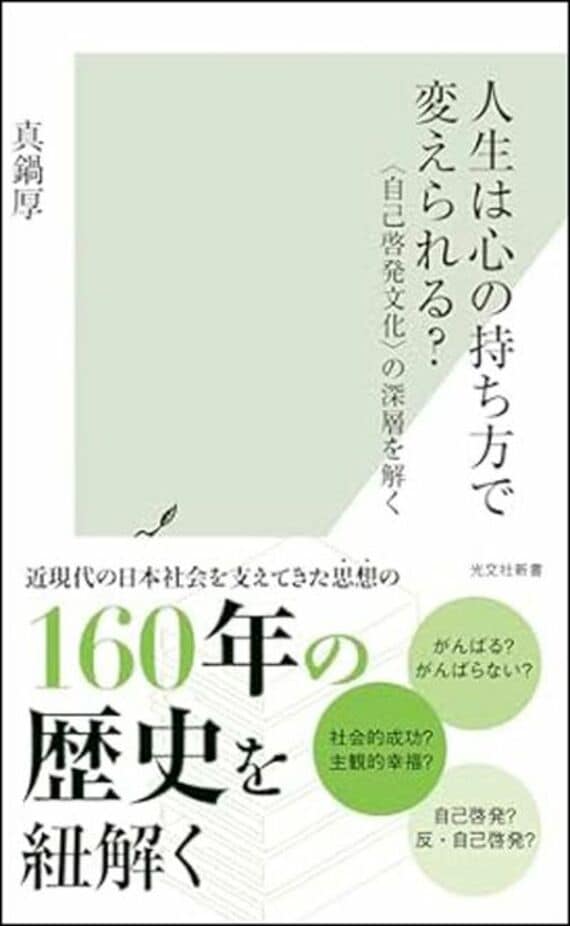































無料会員登録はこちら
ログインはこちら