一方、社会教育は「社会教育法」によって定められ、学校教育以外の教育や文化的活動のすべてを包括しています。そのため、社会教育が対象としている範囲はとても広く、対象者も多様です。
このように広範で多様な取り組みは、学校教育制度のように決まった制度をつくって運営していくことが難しいので、あくまで自発性にもとづいて組織的におこなわれるものとされています。
たとえば、どこの市区町村にも図書館や公民館があると思います。自治体が運営しているスポーツセンター、博物館、宿泊施設もしばしば見られます。これらの取り組みは、すべて社会教育としての「公教育」の一環だといえます。
学校では「教員」が「公教育」に従事していますが、社会教育では社会専門職と呼ばれる社会教育主事、公民館主事、図書館司書、学芸員などが従事しています。
公教育と私教育を協働させる時代へ
社会教育の大きな特徴は、「自発性」だといえます。私は、自発性が私教育との接続点になると考えます。あくまで「公教育」は多様な教育活動のなかから「私教育」を除いたものにすぎません。
人類史を振り返れば「私教育」のほうが長い歴史を持ち、また多様におこなわれてきました。
「教育→仕事→引退」という3ステージ型の人生では、学校教育から社会教育に移っていくイメージが一般的でした。学校教育でも多様化というよりも画一性や価値の一元化がおこなわれ、社会もまたこのような「学校化」(I・イリッチ)が進んだといわれています。
しかし、これからはそれぞれが複線的に人生を歩むマルチステージ型の人生になります。それに伴い、フリースクール、オルタナティブスクール、インターナショナルスクールなどの私教育が注目を集めています。
この時流を踏まえると、「公教育」のなかでは、学校教育と社会教育を連動させること、さらに「公教育」自体も「私教育」や産業と協働し、多様な教育ニーズを満たしていくことが重要なのではないでしょうか。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

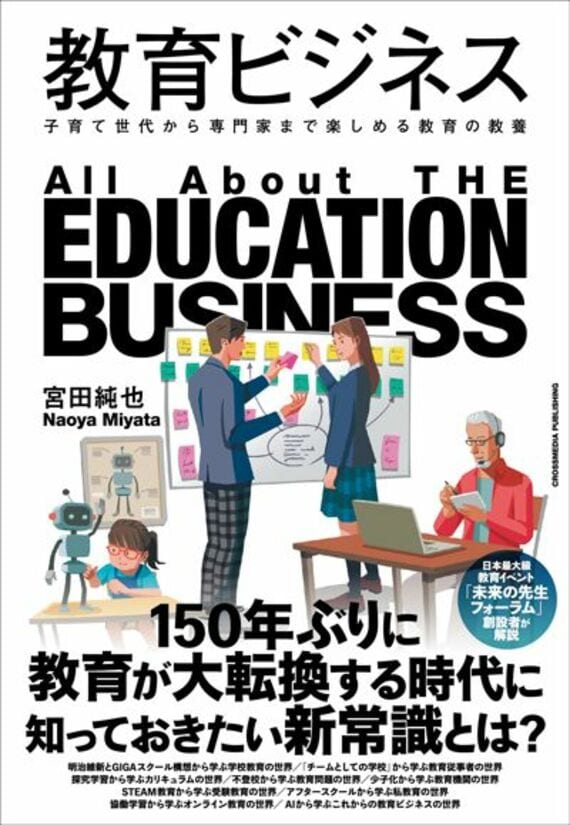






























無料会員登録はこちら
ログインはこちら