「若者上げ、中高年ディス」はなぜ起きるのか? 会社の失敗が世代対立にすり替わる構造
終戦80年を迎える2025年のいま、竹槍と学徒動員が日本企業において繰り返されようとしている。これが日本の若者が置かれた(危機的な)構造である。
この問題に対する直近の動きとして、新卒初任給が上昇している。賃金の伸び悩みや社員への投資の欠如を問題視してきた本書の文脈からすれば肯定的にとらえるべきだ。
ただ手放しでは褒められない。初任給が「朝三暮四」である危険はある。また、初任給がいくら上がっても労働者の給料の多寡は賞与で決まるケースは多い。さらに言えば、初任給の額面よりも長期的な視野で社員への投資が行われるかが重要である。
若者上げ、中高年ディスの欺瞞
なにより年の功を否定するのは、組織の教育訓練能力を自ら否定することに等しい。その齟齬に対応する言説が「若手はオジサンよりデキる」なのだろう(なぜか男性だけ槍玉に挙げられる)。日本の停滞はオジサンのせいだ。だからオジサンから主導権を奪い、退場させないといけない。若者はすごい。ダイバーシティを尊重するし環境意識も高い。だから若者に与えよう……そんな安直な神話を信じたところで、それはほとんど根拠がない構築物だし、会社が良くなることもない。
若者を怖がる根源には立場の転倒がある。とりあえず若者にベットしておこう、際立つように中高年をディスっておこう、と社会が思い始めているような気がする。
竹槍と学徒動員という現実から目を背けて若者を礼賛する流れが、神風特攻隊を生まないことを切に願う。若者にはちゃんと帰りの燃料も準備して生き延びて成長してほしい。何より若者を戦場に送らずに済むよう、年長者が毅然と働ける会社と社会であるべきだ。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

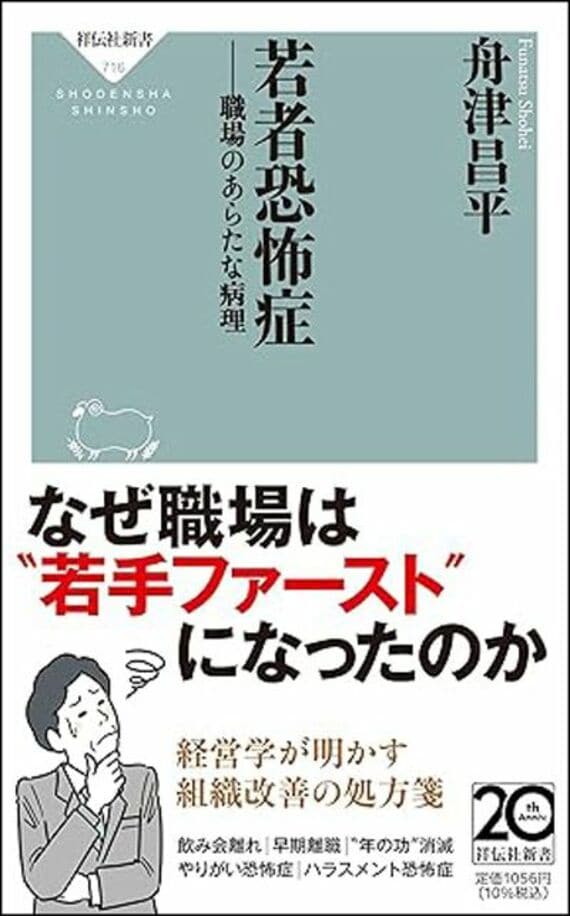
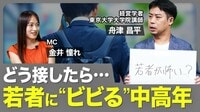





























無料会員登録はこちら
ログインはこちら