「若者上げ、中高年ディス」はなぜ起きるのか? 会社の失敗が世代対立にすり替わる構造
確かに、ホワイトカラーの業務はデジタル中心となっている。ただ、デジタルであろうと20代のほうが仕事ができるならば、そうなってしまう会社の構造を疑うべきである。既存社員が熟練効果を享受できていないのは世代や個人だけの問題ではない。会社組織としてキャリア支援や仕事の采配に失敗してきた結果のはずなのだ。
20代社員が入社すぐにデジタル技術を使いこなしオジサン社員をごぼう抜きにしたとしよう。Z世代すごいぜ! 老害終わってるぜ! と言いたくもなろうが、冷静に見て、それは中高年のリスキリングに「会社が」失敗しているのである。
PCが仕事の主役でなかった時代から次第にデジタル作業が価値創造の核心にかかわる時代に移っていったとして、入社時点でデジタルスキルがない(というよりスキルの必要性が認識されていなかった)社員には会社が支援するのがスジだろう。だって会社の仕事に要るのだから。それを自助努力に丸投げするのはまさに竹槍ではなかろうか。
もし既存社員を凌駕する若手スター社員がいれば、若手の能力の高さよりも先に会社のしょぼさに注意を払うべきだ。若者本人も注意したほうがよい。君がすぐさま輝ける職場はたぶん君がすごいのではなく会社がしょぼいのだ。
学徒動員の未来は覆るか
ここまで見てきた通り、今後の日本では、熟練社員の退場にともなって質的にも(熟練効果の喪失)、量的にも(相対人口の不足)、人手不足が起きていくと予想できる。結果として若手社員を念入りに教育し力をつけてから独り立ちさせる余裕がなくなり、訓練する間もなく若手を前線に送り込むことになる。まさに「学徒動員」である。

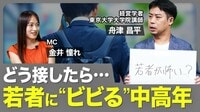





























無料会員登録はこちら
ログインはこちら