どこか似た者同士ともいえる「トランプとプーチン」 2人を結びつける《ストロングマン》への強いこだわりとは
スティーブン・レビツキーとダニエル・ジブラットは『民主主義の死に方』において、トランプによってもたらされたアメリカ社会の変容を次のように描いている。
自国中心主義の延長線上にあるマッドマン・セオリー
これは、トランプがマッドマン・セオリーを用いて、目の前の交渉相手だけでなく、アメリカ社会そのものを自らに都合のよい形に変容させていることを物語っている。トランプとプーチンは、まさに世界の二大マッドマン・セオリー実践者である。
この2人が相互に親近感を抱くのは、ごく自然なことであろう。
さらに2人に共通するのは、自国中心主義の姿勢である。トランプが「アメリカ・ファースト」を繰り返し唱えるように、プーチンもまた「何よりもまずロシアを」と主張し続けている。
こうした姿勢は、グローバリゼーションによって疲弊した国民の不満を吸収し、ストロングマンとしての立場を強固なものにしている。
常識では測れない言動で交渉相手や国民の思考を攪乱し、交渉を優位に進めるという点で、マッドマン・セオリーは自国中心主義の延長線上にある。そしてその根底には、自己と国家とを一体視する強い心理的傾向が存在している。
このように、両者の政治的方向性や野心には顕著な類似点が見られる。すでに自らの政治理念を実現化しているプーチンに対し、これから実現しようとしているトランプが親近感を抱くのは当然である。また、プーチンにとっても、トランプは歓迎すべき政治的同胞として目に映っているのだろう。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

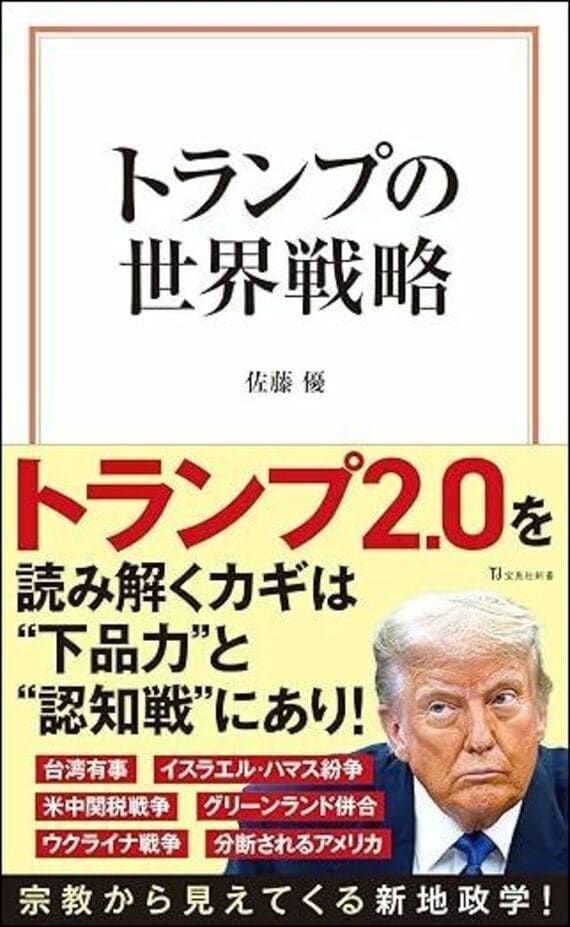






























無料会員登録はこちら
ログインはこちら