奈良メガソーラー造成現場で「土砂2度流出」… それでも止まらない開発の行方
原告は、大雨などの際、下流域の小河川や水路があふれることがないよう、開発地内に調整池を設けて下流河川・水路への悪影響を減らすことが重要であるという点に着目。国土交通省や林野庁などの法令、他府県の状況を精査したうえで、林地開発を許可する際に奈良県が行った審査や指導は誤りであったと論じた。
2025年3月25日、奈良地裁(和田健裁判長)は、奈良県による審査基準の設定や運用に裁量権の逸脱またはその乱用があったとは認められない、として原告の主張を退けた。
住民側が抱いた不信感
そもそもこの提訴の背景には、林地開発をめぐる奈良県の審査や運用について、住民側が大きな不信感を抱いたことがある。
原告の一人で、平群のメガソーラーを考える会の代表世話人、須藤啓二さんは、1級土木施工管理技士の資格を持ち、下水道の水処理施設の設計・施工を行う会社を経営している。4年前、事業者が県に提出した書類を情報開示請求により取り寄せて読み進むうちに、須藤さんは「えっ、なんやこれは」と声を上げ、手を止めた。
事業者は2019年に林地開発許可申請を出し、同年秋に許可を得ている。須藤さんがチェックしていたのは、このときの計算書。「ha2」と書かれた書類を見つけたのだ。ヘクタールは面積の単位で、その二乗というのはあり得ない。
須藤さんは仕事柄、設計や施工に関する様々な書類を行政に提出し、審査を受けてきた。書類審査ではまず単位の間違いをチェックされることから、同じようにメガソーラー事業者側の書類の単位チェックから始めたわけだ。さらによく見ると、奇妙な数字に気づいた。計算書には、下流河川の22カ所における勾配がすべて「180‰」と書かれていた。‰(パーミル)は1000分の1で、%に直すと18%。道路構造令が定める勾配の上限は12%。どの地点でも18%の急勾配であるということはあり得ない。






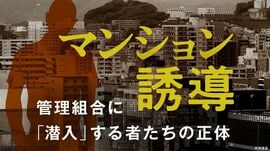
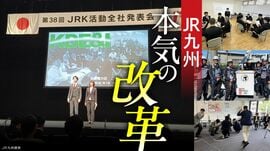
























無料会員登録はこちら
ログインはこちら