奈良メガソーラー造成現場で「土砂2度流出」… それでも止まらない開発の行方

事業者による工事の許可申請書によると、切土、盛土とも100万㎥以上に及び、渓流の上に盛土をする「谷埋め盛土」が行われている。
京都大学などの研究者らによる「国土問題研究会」の「平群メガソーラー調査団」は5月末に現地調査を行い、渓流や湧き水の水抜き・排水対策が十分ではなかったと推察している。調査団は、崩落した盛土付近に水が噴き出して生じた穴を確認した。
造成地の土は、真砂土と呼ばれる水の浸透性が高い土。それほど強くない雨でも雨量が多いと盛土の中に水が貯留され、崩落の原因になる。
6月18日に行われた平群町議会の一般質問。住民団体「平群のメガソーラーを考える会」代表世話人で町議会議員の須藤啓二さん(73歳)が事故原因を尋ねたところ、町は「4.5haの盛土が崩落し、仮設調整池に土砂が流入して土堰堤が破堤した」として、盛土の崩落が原因だったことを明らかにした。

建設現場は大阪のベッドタウン・平群町が誇る「平群の山」
平群のメガソーラーを考える会の金澤清美さん(72歳)と山岡由紀さん(69歳)が、建設現場の山全体を見渡せる場所に連れていってくれた。

金澤さんは40年ほど前に平群町に引っ越してきた。「メガソーラーの造成現場になっているあたりを歩き回りました。山野草がたくさん、ノウサギもいました。川には蛍が飛んでいました。蛍は、ここ数年、泥が流れるようになっていなくなったんです」と話す。






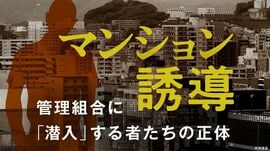
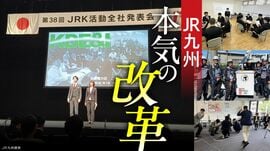
























無料会員登録はこちら
ログインはこちら