ところが、客室稼働率は横ばい、もしくは若干下回っているそうだ。なぜなのか。

高稼働より高単価を重視する収益モデル
実はイシン・ホテルズ・グループは、あえて稼働率を上げすぎず、客室平均単価(ADR)を引き上げることに注力している。その理由は連泊の価値にある。国内客は1泊がほとんどなのに対し、インバウンドは3〜5日の連泊が多い。
よって、土日だけ国内客で稼働が埋まると、5連泊のインバウンドが予約検索をしたときに「空室無し」と表示されてしまう。すると、「残りの4泊分」の売り上げがとれなかったことになるのだ。
「稼働だけを追い求めると、連泊需要の機会損失につながる可能性があります」とオペレーション統括の山本氏は話す。そのため、周辺ホテルの価格設定や需要の推移を細かくキャッチアップし、客室単価を戦略的にコントロール。安値にして即座に予約で埋まることを避け、より高い収益につながる連泊客による収益の最大化を優先している。
国内客を避けているわけではないそうだが、よりインバウンドに特化した戦略といえそうだ。

業績は好調だというイシン・ホテルズ・グループ。運営会社のため、その収益はホテルの売り上げとイコールではない。けれど目安として、運営する17ホテルの売り上げを合計すると、2024年は111億円を達成した。今後は「the b」をブラッシュアップしたブランドも含め、100以上のホテル運営を目指している。

そのための一手として、採用面接のAI化をはじめたばかりだ。このAIでは、外国人スタッフの日本語レベルもチェックでき、採用にかける人的コストが大幅に下がったという。
一方で、自動チェックイン機の導入などスマート化については、コスト対効果の観点から慎重だ。自動チェックイン機は2ホテルに導入しているが、人件費は大きく減らず、導入コストのほうが大きかったそうだ。

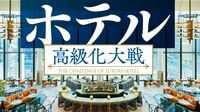





























無料会員登録はこちら
ログインはこちら