カーデザインというと、デジタルツールが多用される中でも、最初にスケッチを描き、それをクレイで立体に仕立てていくという、アナログなプロセスが思い浮かぶ。しかし、AFEELA 1では開発の冒頭から3Dデータを用いたという。
これはソニー流のプロセスで、ホンダ側は面食らったそうだが、バッテリーやセンサーなどの配置条件の決定などのため、データ検証から始めたという。既存のクルマとは別次元の滑らかなフォルムは、この進め方によるところが大きいのだと感じた。
とはいえ、造形の過程では、やはりクルマづくりの経験が豊富なホンダを尊重するシーンも多かったようだ。

「ルーフラインの決め方ひとつとってもさすがで、『どこにピークを持ってくる』などを一瞬で見抜いて修正する。サーフェスの完成度も高く、効率的な検証ができました。デザイナーの意図を汲んで、すぐに具現化できるチームワークとスピードも素晴らしいと思いました」(石井氏)
「クルマは大きなモノであり、デザインするときは目線や視野をずらしながら、遠くからぼんやり見ることも大事です。そのため、ソニーから来た役員の人たちなどにクレイモデルを見てもらうときには『近づかないでください! まずはこの線から見てください』と、モノの見方を含めて進めていきました」(河野氏)
クルマらしさをどれだけ消していくか
開発を進める中で徐々に「クルマらしさ」を加えていったことも、そのひとつかもしれない。
2023年のCESとジャパンモビリティショーで展示された最初のプロトタイプは、『クルマらしさをどれだけ消していくか』という視点で進められたが、動体としての魅力を表現するために、ドア下のパーツの造形をシャープにするなど、走りを感じさせるアプローチが少しずつ加えられていった。

ちなみに当記事で掲載している写真は、2024年のプロトタイプをベースに、 ADAS(先進運転支援システム)のセンサーなどをアップデートしたもので、これから発売されるAFEELA 1とは異なる部分があることを付け加えておく。


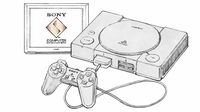



























無料会員登録はこちら
ログインはこちら