
知識の応用が求められる共通テスト
みなさんは、令和の大学受験と、平成・昭和までの大学受験には、どんな違いがあると思いますか?
いろんな違いが思い付くと思います。「一般選抜入試、つまりペーパーテスト一発勝負で大学に入る人がほとんどだったのが、それ以外の総合型選抜入試や、学校推薦型選抜入試といった面接・学校の評定・評論文などが必要とされる入試形態が増えた」とか、「『情報』のような科目が増えたり、『英語リスニング』のように配点が高くなる分野も増えた」など、いろんな違いがあると思います。
でもいちばんは、やはり「知識量があれば解けたセンター試験」と「思考力が必要な共通テスト」の違いではないかと思います。昔のセンター試験であれば、「○年にこういうことをやった人物の名前として、正しいものを4つの選択肢から選びなさい」というような問題が出題されて、知識を暗記すれば解ける問題が多かったです。
それが、共通テストに変わった結果、知識量を前提としつつも、長い問題文を読解し、知識を応用して解かなければならない問題がほとんどになっています。

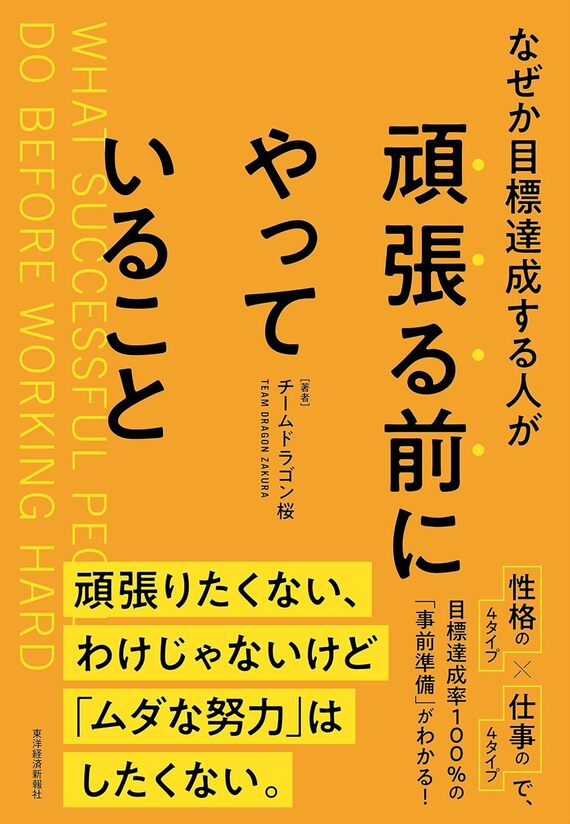






























無料会員登録はこちら
ログインはこちら