使い方も多様化しています。家庭での利用(B2C)だけでなく、企業での活用(B2B)も急速に広がっているのです。オフィスで活用することによる社内コミュニケーションの促進、新入社員教育支援、店舗での顧客対応サポートなどです。
コクヨなどが行った調査では、約4割の人が「コミュニケーションロボットがいるから出社しよう」と出社の動機になるといいます。実際に87.6%の従業員がロボットのおかげでコミュニケーションが活性化したと感じています。
このような背景から、会社の福利厚生の一環としてロボットの導入が進められる事例も出てきています。
AIロボットとの共存時代の幕開け
もちろん、課題がないわけではありません。
ロボットが収集する個人情報の管理といったプライバシーの問題や、より複雑な環境下でのロボットの音声認識、画像認識、データ分析などの能力は、今後さらなる対応が必要になってくるでしょう。
特にプライバシーの問題は、欧州で制定された「一般データ保護規則(GDPR)」など個人データの保護とも関連し、人の身近な場所で使われるロボットならではのアプローチも必要になってくるかもしれません。
これらの課題を克服しつつ、人間とロボットが共生する社会の実現に向けて、着実に技術開発と社会実装が進められています。
コミュニケーションロボットの再ブームは、単なるガジェットの流行ではありません。
AIロボットとの共存時代の幕開けを告げる重要な現象なのです。今後、私たちの生活や仕事がどのように変わっていくのかに影響するひとつの要素であることは間違いなさそうです。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

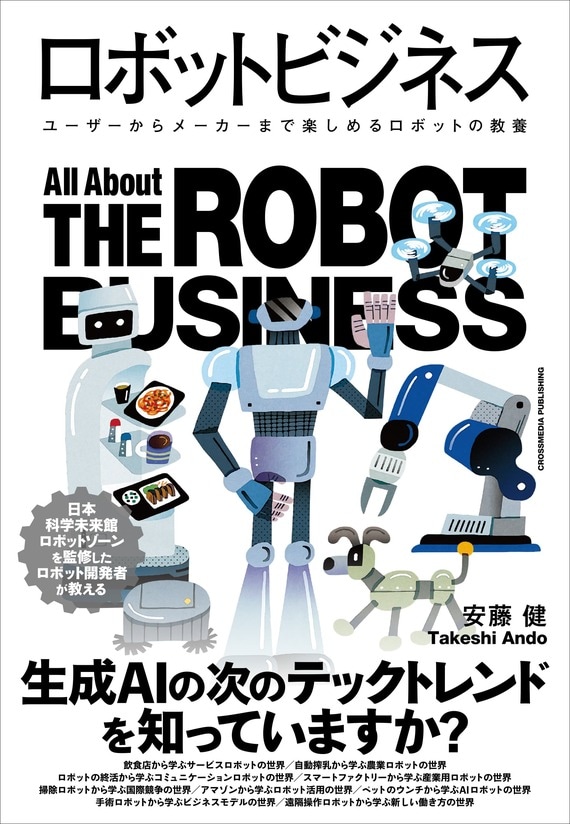






























無料会員登録はこちら
ログインはこちら