
「管理職=罰ゲーム」
日本のビジネスシーンでは近年、管理職につくことが「罰ゲーム」になっていると言われています。
それもそのはずです。日本の管理職の仕事は名実ともに増えていますし、変容もしています。
部下の管理監督だけではなく、コンプライアンスにも対応しなければなりません。部下とのコミュニケーションも変化を求められています。
働き方改革により、部下の業務時間が減ったことで、部下の仕事を代わりに請け負っている人もいるかもしれません。
上からも下からもプレッシャーをかけられる。しかも、部下の育成はうまくいかないし、業務量は増えるし、後任もいない。
多くの新卒入社社員は、会社を辞めない限りは、入社以来ずっとこの昇進レースを続けることになるわけです。
新卒4年目くらいから、そういった「つらそうな未来」が見えてくる。
そのため、前回の記事(日本企業で「新人と役員」以外が、情熱をもって仕事ができない根本理由)で解説したように、「エンゲージメントスコア」(従業員と組織の「

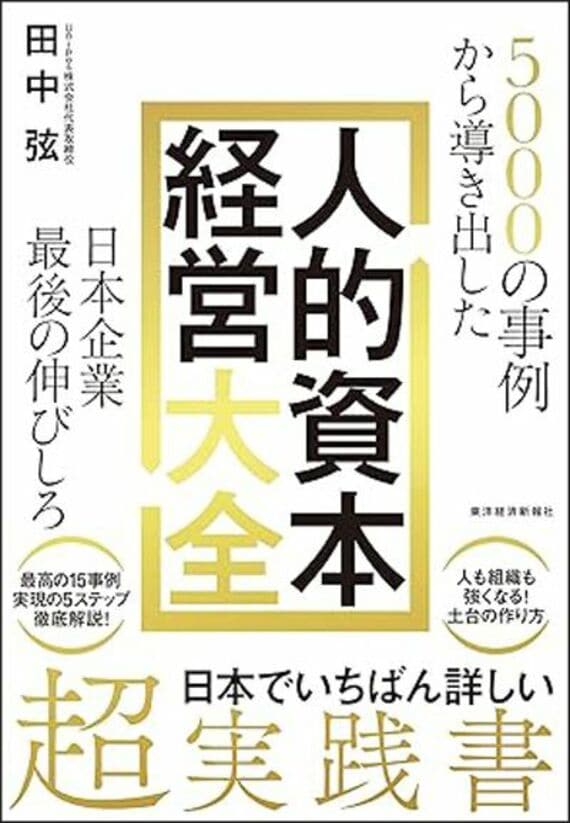






























無料会員登録はこちら
ログインはこちら