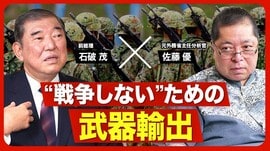燃え盛るドラム缶「30年前の大阪・西成」で見た現実 覚醒剤の路上密売人は消え、小中一貫校が新設も残る課題

長年通ううちに知り合った釜ケ崎のガイドを続ける漫画家のありむら潜(せん)さんのほか、まちづくり、ホームレス研究、労働経済、ソーシャルワークといった専門分野を持つエキスパートを集め、「7人の侍」を結成。行政や警察に対する住民側の根強い不信感を払拭(ふっしょく)するため、会議はフルオープンにこだわった。
「府市あわせ(不幸せ)」と揶揄(やゆ)される大阪府と市の対立など、様々な壁が立ちはだかった。鈴木さんは「この地域はどん底の状態。お互いいがみ合っていても、このままでは共倒れする危機感は共通していた」と振り返る。
反対の立場の人とも辛抱強く話し合い、「一歩一歩、ほふく前進」で着地点を探った。こだわったのは「全員参加のまちづくり」だ。
2014年9月22日。35人の委員がメンバーとなった第1回「あいりん地域のまちづくり検討会議」の様子が動画投稿サイトに残っている。
「現場に行ったことあるんか」「おまえらに何がわかるんだ」。聴衆らも含め、二百数十人が集まった萩之茶屋小学校の講堂で、怒号が飛び交っていた。
「ここには労働者団体の代表もいれば、町内会、支援者、子育ての代表もいれば、いろんな人がいます。オープンの場で話してもらっています」
覚醒剤の密売人は姿を消し……
鈴木さんは会議を続けようと懸命に説得を続けた。その後、会議は6回を重ね、提案書は市長と府知事に手渡された。
その後、住民投票を実施した大阪都構想の否決を受けて橋下市長が退任。鈴木さんも2015年11月に特別顧問を退いた。「改革には強烈な反発もあり、誰かが責任をとらないといけなかった」。
不法投棄されたごみを回収する清掃業などでホームレスの雇用を生み、子育て世帯を呼び込もうと小中一貫校も新設した。あちこちにいた覚醒剤の密売人は姿を消し、治安も改善した。
鈴木さんは成果を感じる一方で、特区構想の「第二の矢」として掲げていた経済活性化、人口流入がまだまだ進んでいない現状が気になっている。当時、活性化の目玉として考えていた、台湾やタイの夜市のような大規模な観光客向けの屋台村も実現していない。