日産・ホンダ「統合破談」で迎える三菱自の分岐点 単独路線の限界を認識、三菱グループに決定権

「焦る必要はない。我々の強みが生かせる形を見極めるだけだ」
ホンダと日産自動車の経営統合が破談濃厚となる中、三菱自動車工業の幹部はそうつぶやいた。
2社が協議していた経営統合に、三菱自は「参画・関与およびシナジー享受」の可能性を検討していた。1月末には検討結果を出す予定だった。が、2社の協議が進まないため、正式なスタンスを明らかにできないでいた。
結局、土台となる2社の経営統合が雲散霧消したことで、三菱自の先行きも不透明感が増している。
「参画の形」を決めるのは三菱グループ
もともと三菱自が2社連合に「参画・関与」することは既定路線で、もっぱら検討されたのは「どのような形」であるかだった。ホンダ、日産に倣うなら、持ち株会社の傘下に100%子会社となるのが自然だが、この案は早々に見切られていた。
というのも、三菱自に大きな影響を持つ三菱グループが持ち株会社方式に抵抗感が強かったからだ。
三菱自はグループの中核である三菱重工業の自動車部門を源流に持つ。現在も三菱商事が20%の株式を保有する大株主であり、重工や三菱UFJ銀行の出資も残っている。
三菱自の社外取締役13人のうち4人が商事や重工、銀行の出身者。営業担当の中村達夫副社長は商事、松岡健太郎副社長兼CFO(最高財務責任者)は銀行からの移籍組だ。とくに商事とは東南アジアを軸に販売やアフターサービスで強力な支援を受けており、歴史的にも人材面でも、事業上も関係が深い。
だが、持ち株会社での経営統合の場合、三菱自の時価総額はホンダの13分の1、日産の3分の1しかないため、同社株主の持ち株会社への出資率は6%程度にとどまる可能性が高い。つまり、持ち株会社に対する三菱グループの出資比率は1%台となり、経営への影響力を失ってしまう。しかも、上場するのは持ち株会社で、傘下の事業会社は上場廃止となる。
この点も三菱グループにとってネックとなったようだ。「三菱自に決定権はない」。ある三菱自幹部は率直にそう語っていた。


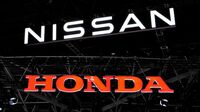





























無料会員登録はこちら
ログインはこちら