峰にかかる幾重もの雲が、宮を思う心も隔てている気がして、しみじみと悲しく感じられる。なおのこと、この姫君たちのお気持ちはどんなだろうと思うといたわしく、さぞやもの思いの限りを尽くしていることだろう、こうして世馴れない様子でいるのも無理はない、と中将は思わずにはいられない。
「あさぼらけ家路(いへぢ)も見えず尋(たづ)ね来(こ)し槇(まき)の尾山(をやま)は霧こめてけり
(ほんのりと夜が明けていきますが、帰るべき家路も見えないくらい、はるばるやってきた槇の尾山(おやま)は霧が立ちこめています)
心細いことです」と引き返して出立(しゅったつ)をためらっている中将の姿は、こうした貴人を見馴れている都の人でも、やはり格別にすばらしいと思うのだから、ましてこの山里の人たちの目には、見たこともないみごとなお方だとどうして映らないはずがあろうか。女房たちが返歌の取り次ぎもしづらそうにしているので、大君は先ほどと同じようにひどく遠慮がちに、
雲のゐる峰のかけ路(ぢ)を秋霧のいとど隔つるころにもあるかな
(雲のかかっている峰の険しい路(みち)を、さらにまた秋霧までが、父君とのあいだをいっそう隔てているこの頃です)
ちいさくため息を漏らしている様子は、深く人の胸に染み入るようである。
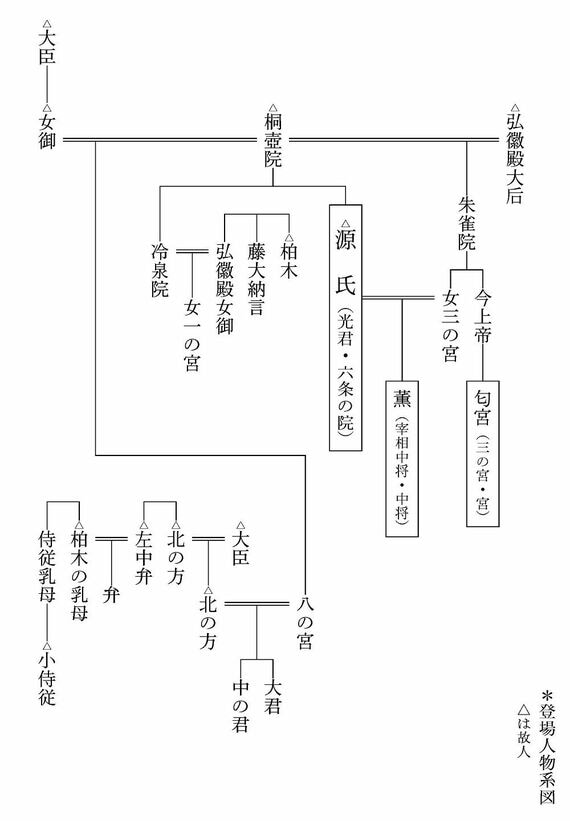
思えばだれもみな同じような無常の世の姿
どれほどの風情がある山里でもないけれど、いかにもいたわしく感じられることが多く、中将は帰りがたいのだが、次第に明るくなっていくので、さすがに顔を見られるのも恥ずかしく、
「なまじお言葉をいただいてしまったので、なおお話ししたい気持ちが増しましたが、もう少し親しくなってから恨み言を申すことにしましょう。それにしてもこのように、世間並みの男と同じような扱いでは心外ですし、ものごとをおわかりにならないのだなと恨めしく思いますよ」と言い、宿直人(とのいびと)が用意した西面(にしおもて)の部屋に行き、もの思いに沈む。
「網代のあたりはずいぶんと騒がしい。けれども氷魚(ひお(鮎(あゆ)の稚魚))も近づかないのだろうか、なんだかぱっとしない感じだけれど」と、網代にくわしいお供の人々は話している。みすぼらしい舟の何艘(そう)かが刈った柴を積んでいる。それぞれに、なんということもない生業(なりわい)のために行き交って、はかない水の上に浮かんでいる様子は、思えばだれもみな同じような無常の世の姿である。「この自分はそんなふうに浮かぶことなく、玉の台(うてな)に安泰でいられる身の上だと思えるような世だろうか」と中将は考え続ける。「さむしろに衣(ころも)かたしき今宵(こよひ)もや我を待つらむ宇治(うぢ)の橋姫(古今集/むしろに自分ひとりの衣を敷いて、今宵も私を待っているのだろうか、宇治の橋姫は)」を思い出した中将は、硯を持ってこさせて、大君に文を送る。




























無料会員登録はこちら
ログインはこちら