「十九におなりでございました。わたくし右近は、女君の乳母の子でございました。その母がわたくしを残して亡くなりましたので、女君のおとうさまである三位の君がわたくしをかわいがってくださいまして、女君のおそばで育ててくださいました。そのご恩を思い出しますと、女君は亡くなったのに、わたくしがこの先どうして生きていかれましょう。女君とあれほど親しくさせていただいたことが、悔やまれるほどでございます。見るからにか弱い女君を、ただ頼りにして長年過ごして参りました」
「か弱い人のほうがずっといい。賢すぎて我の強い女性はまったく好きになれないよ。この私がしっかりしていないからかもしれないね。素直で、うっかりすると男にだまされそうで、それでいて慎み深く、夫を信頼してついていく女性がいちばんいい。そういう人にあれこれと教えながらいっしょに暮らして、成長を見守っていけば、情も深まるに違いないだろうね」
その光君の言葉を聞いて、
「まさに女君はそのようなお方でございましたのに、本当に残念なことでございます」
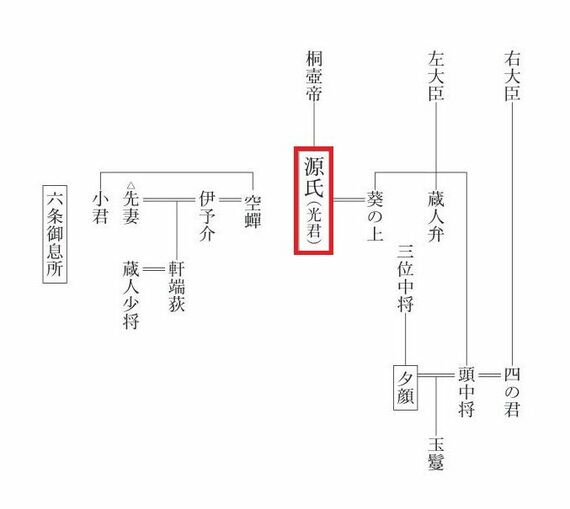
胸がふさがれる思い
右近は泣き出してしまう。空が曇ってきて、風が冷たく感じられ、光君はしんみりともの思いに沈む。
見し人の煙(けぶり)を雲とながむればゆふべの空もむつましきかな
(恋しい人を葬った煙があの雲になったと思うと、夕方の空も親しく思えてくる)
と独り言のようにつぶやくが、右近は返歌もできない。自分がこうして光君のおそばにいるように、女君も生きていらして、お二人が並んでいらっしゃったのならどんなにすばらしいだろうと、胸がふさがれる思いである。
あのちいさな宿で、うるさいと感じた戸外の砧の音も思い出すと恋しくなり、光君は「八月九日正(まさ)に長き夜 千声万声了(や)む時なし」と、白楽天(はくらくてん)の詩を口ずさみながら横たわる。
































無料会員登録はこちら
ログインはこちら