光君が全快したのは九月の二十日頃だった。ひどく面やつれしているが、かえって気品が出て、うつくしさに磨きがかかったようである。その光君は、しょっちゅうもの思いに沈んでは、声を出して泣いている。それを見て不審に思う女房もいて、物の怪が憑いてしまったのではないかと言い合った。
ある穏やかな夕暮れ、光君は右近を呼んであれこれと思い出話をしていたが、ふと言った。
「やっぱり合点がいかないな。あの人は、どうして自分の素性をあんなにも隠していたのだろう。本当に『ただの海士(あま)の子』だったとしても、あれほど思っていた私の心を何も知らないかのように頑(かたく)なに隠しているんだから、恨めしかったよ」
すると右近が言う。
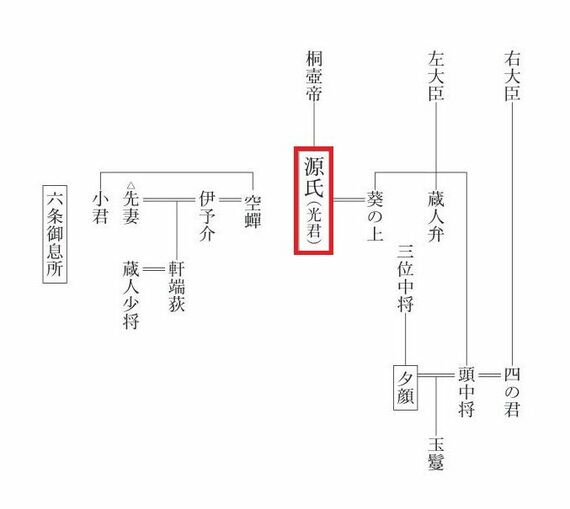
つまらない誤解
「どうしてご主人さまが頑なに隠したりなどなさいましょう。そもそもあんなに短いあいだのことです、ご自分からいつ名乗ればよいのかおわかりにならなかったのではございませんか。最初から、異様な出(い)で立ちでこっそりいらしてましたから、本当に現実のこととは思えないとご主人さまはおっしゃっておいででした。あなたさまがお名前を隠していらっしゃっても、どなたかはうすうすわかっておいででしたよ。それでも、ただの気まぐれで、本気ではない遊びのお相手だから源氏の君とみずからお名乗りなさらないのだろうと、そのことをつらく思っていらっしゃいました」
「お互いにつまらない誤解をしたものだな。そんなふうに隠しておくつもりはなかったんだ。ただ、ああいう許されない関係ははじめてのことだった。主上(おかみ)からお小言をいただくし、ほかにもいろいろと気を遣う。女の人に軽口を叩いてもすぐに知られて評判になってしまう。でもね、あの夕方のできごとから、あの人のことがどういうわけか忘れられなくて、無理を押してでも逢いにいってしまった……それも思えば、こうしてすぐに別れてしまう縁だったからだね。そういうことだったのかと思いもするし、恨めしくもある。こんなにはかなく終わる縁なら、あんなに私を惹きつけないでくれればよかった。ねえ、もっとくわしく話しておくれ、もう何も隠す必要はないじゃないか。七日ごとの法要の供養も、名前がわからなくてはだれのためと祈願すればいいんだい」
それを聞くと、右近は口を開いた。





























無料会員登録はこちら
ログインはこちら