昭和初期の金解禁をめぐる議論の中で、湛山は金と円の交換レートを足元の経済状況に合わせた新平価とすべきだと主張していた。だが、浜口内閣の井上準之助蔵相は従来レートの旧平価で金解禁をすることを決め、失敗してしまう。その結果、軍部の台頭やテロの頻発をもたらした。
この苦い経験が湛山に、自ら政治家となり現実の施策に自身の知見を生かすべきだと決意させるきっかけとなった。
すき焼きが結んだ縁
──湛山は鳩山一郎率いる日本自由党公認で衆議院議員選挙に立候補しました。結果は落選でしたが、無議席で蔵相に起用されます。
制度に鑑みれば、国会議員でなくとも国務大臣にはなれた。ただ、そうした例はあまり多くない。やはり吉田や鳩山から経済知識人として信頼を得ていたからこそ、内閣の要である蔵相に任命されたのだろう。
湛山、吉田、鳩山の3人は戦前からつながりを持っていた。彼らを結び付けていたのは、実はすき焼きだ。湛山はすき焼きが大好物で、戦時中でも牛肉を入手できる極秘ルートを持っていたそうだ。鳩山、吉田を東洋経済新報社に招いて、すき焼きでもてなしたという話が残っている。
すき焼き効果もあるだろうが、金解禁論争の際の湛山の活躍は吉田らも耳にしていたはずだ。このときに、湛山は高橋是清ら大臣クラスに呼ばれ、議論を戦わせたという記録がある。エコノミストとして政界でも名をはせていた湛山だからこその入閣だった。
──湛山はGHQと対立した際、淡々と政策の理を説いています。また対立の結果、公職追放を受けても堂々と抗議文を提出し、マッカーサーの監督責任にまで言及しました。湛山はなぜこうした毅然たる対応を取れたのでしょうか。
湛山の基本姿勢は実践にある。湛山は日蓮宗の僧侶の家に生まれた。日蓮宗の特色は多々あるが、あえて挙げるとすれば実践。相手が間違っており、自分が正しいと思うときには、どんどん相手を説き伏せていく点にある。
日蓮宗の影響に加え、早稲田大学時代に著名な哲学者、田中王堂から学んだプラグマティズムや功利主義などの哲学も、実践を重視する湛山の姿勢に大きな影響を与えた。湛山は、自身の考え方に特徴があるとすればそれは王堂哲学の賜物だと語る。

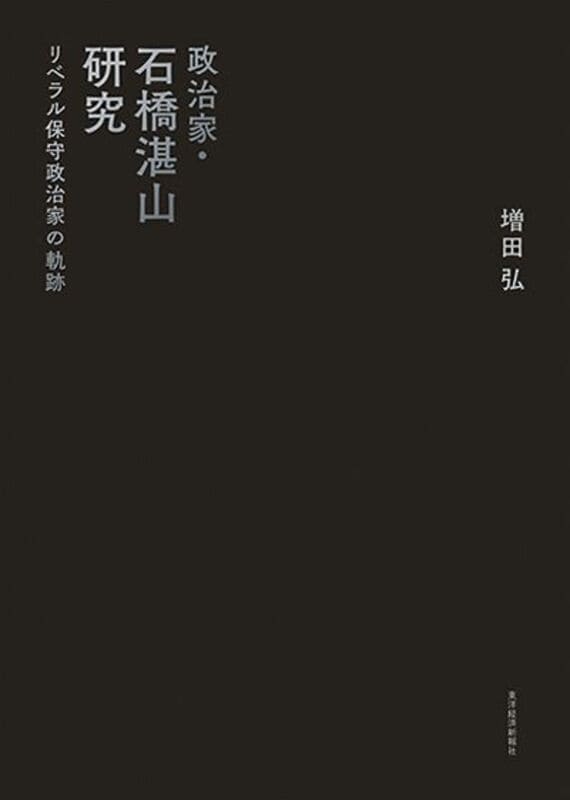
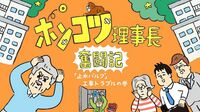





























無料会員登録はこちら
ログインはこちら