このような状態のもとで仕事をクリアしていくことが良質な人生経験となって、次にもっと難易度が高い仕事がきても「なんとかなる」(処理可能感)と思えるようになり、より大きな仕事、困難な出来事にも対処できるようになります。
つまり、適度な課題を与えられてクリアしていくことによる「成功体験」が、処理可能感を高めることに大きくかかわっているのです。
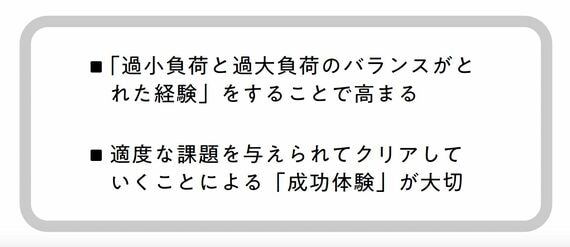
したがって重圧に耐えかねるような仕事で、結局うまくいかなかったりしたら、処理可能感を培うことにはつながりにくいと言ます。「なんとかなった」経験があるから、次も「なんとかなる」と思えるのです。
小さな成功体験を積み重ねる
一方で、「資料のコピーを100枚、15時までに」などのようなストレスのほとんどない仕事で成功しても、これもまた処理可能感を育みにくいと言えます。
大きすぎず、小さすぎないストレスのかかった仕事を経験し、うまくいくことによって育まれるのが処理可能感です。
この「成功体験」は、人に助けてもらった結果でも構いません。あるいは、座学で学んだ疑似体験であったり、人に教えてもらったりしたものでもいいのです。
例えば、一人で仕事を抱え込んでしまって終わりが見えず、「どうしよう」とパニックになっていた社員Kさんのケースです。上司から「あの仕事は、今日が締め切りでしたよね。どうなっていますか?」と聞かれて、Kさんは「実は、ほとんどできてません……」と答え、泣きつきます。
ここで上司は、「そうか、じゃあみんなで手伝って仕上げようか」と言って、他の社員に仕事をふったり、締め切りを数日遅らせたりして、テキパキと指示を出します。
数日後、仕事は、同僚や先輩に手伝ってもらいながら、無事に終わりました。たしかにKさんは、自分一人では仕事が終わらず迷惑をかけてしまいましたが、みんなで無事に終わらせたことで「成功体験」「できた経験」になっています。
結果、Kさんは、「早めに他の人に助けを求めること」「わからないことは人に聞くこと」「必要なときは上司の力を借りること」などを学んでいきます。
こうした体験からも、「こうすれば、次もできる」といった「なんとかなる」感は培われていくのです。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

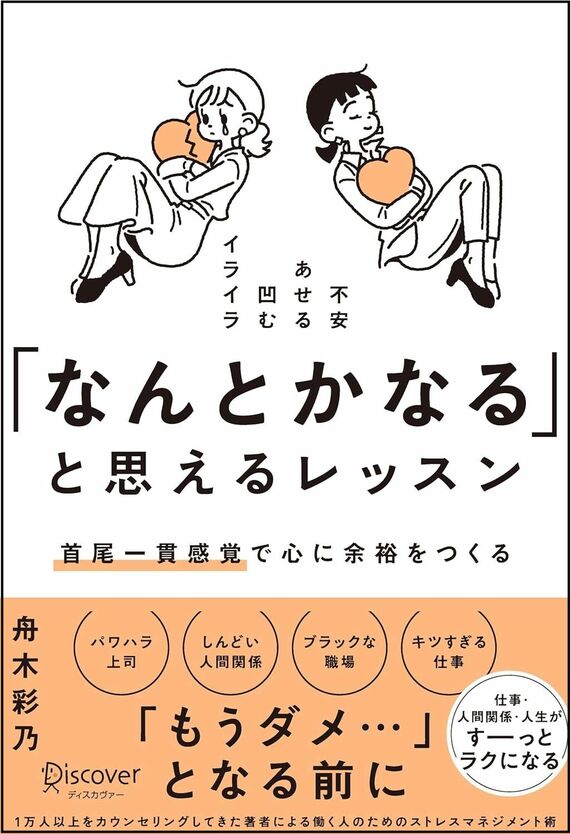






























無料会員登録はこちら
ログインはこちら