「社員の7割が障がい者」チョーク会社の誕生経緯 24時間テレビでドラマ化される日本理化学工業
「その4つの幸せのなかの3つは、働くことを通じて実現できる幸せなんです。だから、どんな障がい者の方でも、働きたいという気持ちがあるんですよ。施設のなかでのんびり楽しく、自宅でのんびり楽しく、テレビだけ見るのが幸せではないんです。真の幸せは働くことなんです」
普通に働いてきた大山さんにとって、それは目からウロコが落ちるような考え方でした。これは、働いている多くの人たちも忘れていることかもしれません。それを障がい者の方によって教えられたのです。
それとほぼ同時期のこと。テレビを見ていた大山さんの目に、「カバ園長」と親しまれていた上野動物園の西山登志雄さんの姿が飛び込んできました。そのとき西山さんはこんな話をしていたそうです。
「最近の動物園の動物は、自分の子どもを育てないのです。どうしてだろうと考えてみたのですが、どうやらオリの中でエサを与えられていると、子どもを育てるという本能を見失ってしまうようです」
つまり、それは、「なんのために生きているのか」を見失っているのと同じことではないか? そう思いあたり、大山さんは衝撃を受けました。
この2つの言葉によって、大山さんは「人間にとって“生きる”とは、必要とされて働き、それによって自分で稼いで自立することなんだ」ということに気づいたそうです。
「それなら、そういう場を提供することこそ、会社にできることなのではないか。企業の存在価値であり社会的使命なのではないか」
それをきっかけに、以来60年以上にわたって、日本理化学工業は積極的に障がい者を雇用し続けることになったのです。
人を工程に合わせるのではなく、工程を人に合わせる
障がい者を受け入れたものの、はじめの頃は苦労の連続だったそうです。どうやって仕事を教えればいいのかもわからない状態です。
普通は自分たちがつくったラインに人間を合わせるものですが、大山さんは、その子たちが精いっぱいの仕事ができるように、一人ひとりの状態に合わせて機械を変え、道具を変え、部品を変えていったのです。
「この子たちは、自宅から会社まで歩いてきたり、バスで来ることもあるけれど、少なくとも信号機のある道路を渡って会社に来ている。ということは、色を識別する能力はあるのだから、それを利用しよう」という具合です。

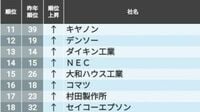





























無料会員登録はこちら
ログインはこちら