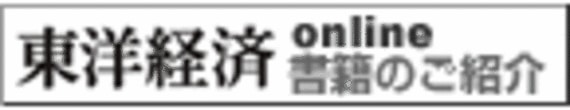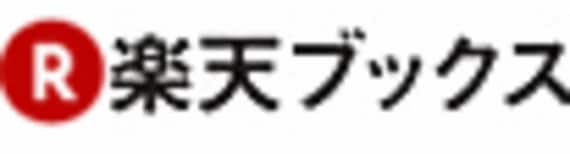「働くこと」を企業と大人にたずねたい これから社会へ出る人のための仕事の物語 中澤二朗 著~働くとは何か 現場からのメッセージ

ビジネスパーソンの職場生活は、転勤や移動あるいは昇進(や降格)など、こもごもの悲喜に彩られている。いつの時代でも「人事」は働く人々の大きな関心事のひとつである。著者は30年を超える企業人としての時間のほとんどを「人事」畑で過ごしており、その歳月から滴り落ちた本書は、「働く」ことに関する示唆に満ちている。
たとえば「やりたい仕事は知っている仕事の中からしか選べない。かたや、成長させてくれる仕事は、知っている仕事の中よりも、知らない仕事の中にあるほうが多い。というのも、知っている仕事よりも、知らない仕事のほうが圧倒的に多いからです。にもかかわらず、限られたやりたい仕事だけにこだわっていれば、もっと自分を成長させてくれるであろう仕事にはなかなか就けない」と語る。
では「成長」とはなんだろう。「それはまだ見ぬ自分との出会い」であり、そして「まだ見ぬ自分に出会うには、まだ見ぬ世界を知り尽くした人に身を委ねるしかない」と本書は語る。それは「あこがれの人にあこがれる」ことである、と。
そうなのだ。とても立派に見える先輩たちもまた、自分たちと同じような悩みや喜びを生きて成長したのだ。
また職場は外部環境の変化にも翻弄される。「姿勢としての終身雇用」を貫くためにどうしたらよいのか。「法人」も「人」であるがゆえに不死身でもなければ永遠でもない。
本書には悔しさ、未練、心痛のともなった「歯切れの悪い決断」としてのリストラのエピソードがある。しかし大切なのはこのことだ。働く者がしぶしぶでも納得するには「会社側の姿勢」が大事だ。
そして著者は、人間の成長にとって欠かせない、他者による「承認」について次のように語る。「<成果の承認>は<産業の論理>に、<人格の承認>は<人間の論理>に対応している」と。それゆえ「成果の承認」には多少の不満があっても耐えられるが「人格の承認」はそうはいかないと指摘する。
「承認」のバランスがほどよくとれている会社などおそらくない。しかし不届き者へのペナルティを含めて、「人事」は「信頼の窓」であることが望ましい。
本書は、「会社とは」「働くとは」の問いを突きつめた、すばらしい「現場からのメッセージ」集であると言っても過言ではない。
玄田有史が巻末の解説で「人間を信頼し尊重するという『人間の論理』が企業の活力である」とする本書のコンセプトを語っているが、それ自体が、時宜に適した「論」となっている。
なかざわ・じろう
高知大学客員教授。1951年群馬県生まれ。75年新日本製鉄入社。鉄鋼輸出、生産管理、労働部門などを経て、人事部門に異動。2001年新日鉄ソリューションズ発足後、同社に転籍。30年近くにわたって、人事・採用全般に携わる。11年4月より現職。
東洋経済新報社 1575円 243ページ
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら