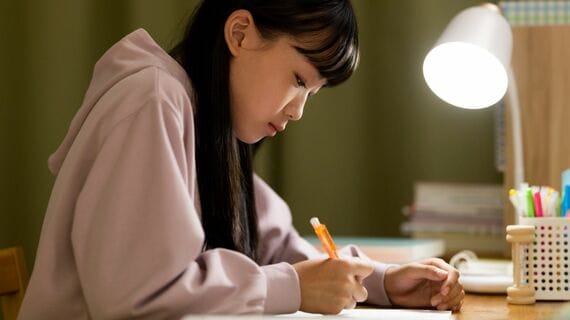
※石田勝紀先生へのご相談はこちらから
宿題は何のためになる?
「宿題」という言葉によいイメージを持つ人は少ないのではないでしょうか。講演会やセミナーで来場者の方に聞くと、「やらねばならないもの」「やりたくないもの」「ペナルティ」とネガティブな感想が続きます。
そもそも、宿題にはどんな意味があるのでしょうか?
宿題といえば、デューク大学のハリス・クーパー教授が有名です。「小中学生の宿題は成績向上に効果なし」と誤読され、当時話題になったのですが、原文には実際には次のようなことが書かれています。
*量とは10分ルール(1学年✕10分)で、それを超えると多い
・宿題は重要であり、小学生よりも中高生の方が効果的
・小学生の場合は学力向上よりも、学習習慣の確立に効果がある
「宿題=勉強」であるため、適切な量であれば効果があることは理解できます。一方、筆者はそもそも「宿題は何のために出すのか?」という視点から考える必要があると思っています。
というのも、長年学習塾を経営してきて、その出し方やり方次第では、まるで無意味なものになってしまうという痛い実感があるからです。































無料会員登録はこちら
ログインはこちら