ヤマハ、「本物」に近づけた電子ピアノの使命 高度な技術力を要する「音の響き」で差別化
カシオのPriviaシリーズ「PX-S1000」はその需要をとらえた。価格は6万円程度にもかかわらず、アコースティックピアノのタッチ感を再現するハンマーアクション機構が付き、88の鍵盤を備えた本格的な電子ピアノであることを売りにする。
ヤマハも3年前の2017年にクラビノーバの新製品に20年ぶりの大刷新となる「グランドタッチ鍵盤」という新たな機構を搭載。鍵盤の支点の位置を一般的な電子ピアノよりも奥にすることで、グランドピアノと同程度までに鍵盤が沈むなど、タッチ感を一気にグランドピアノに近付けた。
ただ、価格は28.2万~42万円と高額。音源にヤマハのグランドピアノはもちろん、2008年に買収したオーストリアの高級ピアノ・ベーゼンドルファーの音を採用し、そのほかグランドピアノの共鳴音をシミュレートして再現する「バーチャル・レゾナンス・モデリング」を搭載し、タッチ感に限らない高機能を搭載している。しかし、低価格で本格派の電子ピアノが増えたことで、相対的にユーザーへの訴求力が落ちていた。
音の再現にもう一段のハードル
今回の「CLP-700」シリーズでヤマハが磨きをかけたのは電子ピアノが苦手とする「音の響き」だ。

電子ピアノよりも数倍大きく、複雑な機構を備えているグランドピアノは筐体自体やダンパー、弦などの内部機構それぞれが異なる響きや動きをすることで演奏者が狙った音が引き出される。
逆に言えば、構造が単純でコンパクトな電子ピアノの音は単調になりがちで、タッチ感が再現されても細かい音の出方や響きまで再現することは難しかった。
実際、2017年の製品ではピアノの共鳴音は再現できたものの、演奏者の繊細なタッチから出る音まで再現するにはもう一段階のハードルがあった。奏者のイメージ通りの音を出すにはタッチの力加減や鍵盤から指を離すときの早さを正確に測定したうえで、その細かい変化を出力できる技術が必要とされる。



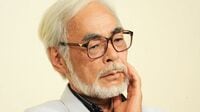




























無料会員登録はこちら
ログインはこちら