「下村治は積極財政の支持者」論に覚える違和感 中野剛志氏の一面的な下村観に異議あり

しかし1973年の10月に起きた第1次石油危機後、自らの主張を180度転換し、ゼロ成長論者となる。均衡主義者としての氏の考え方は変わっていないのだが、劇的な転換の背景には、内外の均衡を達成しつつ日本の高度成長を実現するという条件が、1970年代に大きく転換したことに起因している。
1つは、為替レート制度の大転換である。ニクソン・ショックを経て1973年以降変動相場制へと移行したことにより、下村氏は日本経済の国際収支均衡を支える重要な制度的条件が失われたと判断したに違いない。
もう1つの変化は、日本の技術革新力が頭打ちになったと考えたことである。石油危機は、石油多消費型技術を中心に発展してきた日本が壁にぶつかったことを強く印象づける事態であった。
すでに石油危機以前から、下村氏はキャッチアップした技術に依存した日本の成長力が減速すると考えていたが、この高度成長期の技術のままでは、日本の国際収支が赤字を続け不均衡になると感じたのではないか。その国際収支の均衡を回復させるためには、経済成長を落とし国内需要を低下させることで、国内市場と国際収支の均衡を達成すべきだと考えたのだろう。
もちろん、筆者も含めて多くの経済学者は、上記の見方に容易に反論できる。変動相場制になれば、国際資本の移動によって、毎期の貿易収支の均衡を気にすることなく経済活動を行うことができ、かつ財政金融政策の裁量の幅も広がる。そして日々の為替レートが収支の不均衡を調整してくれるのである。
国内均衡と国際均衡を両立させるという考え
しかし下村氏や堀内氏はこうした制度下での経済運営では、人々の経済社会生活における規律が維持できないと考えていた。下村氏は人々が自ら「節度」ある経済生活を受け入れることで、国内均衡と国際均衡を両立させる持続的な経済状態を想定していた。この想定が経済成長率に置き換えられた状態を「ゼロ成長」と呼ぶのである。
当然のことながらこの「ゼロ成長論」には、政府が財政節度を維持することも含まれる。財政節度とは均衡財政を目指すことにほかならない。
実は中野氏は、近著の『日本経済学新論』(ちくま新書)(以下「新論」と呼ぶ)の中で、第1次石油危機後の下村氏の議論についてほぼ同様のことを述べられている。もしその理解を進めて下村氏の議論に倣うならば、それは積極財政ではなく財政規律の維持であろう。中野氏が「新論」で、下村氏の議論の変遷を丁寧にたどっておられながら、なぜ積極財政の部分だけを東洋経済オンラインで強調されるのかについては、きちんとした説明が必要だろう。



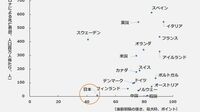





























無料会員登録はこちら
ログインはこちら