次期FRB議長に求められる、第3の使命とは? 雇用や物価と並び、重要視されてきた「低金利」の弊害
おそらく多くの人々は知らないし、本稿でもあえて触れてこなかったが、実はデュアル・マンデートを定めた米国の法律には、最大限の雇用と物価安定と並んで、「低い長期金利」(moderate long-term interest rates)という項目が、使命として掲げられている。
連銀法改正はいつ?
持続的な「低い長期金利」はバブルの温床となり金融システムの安定性を揺るがしうる材料、というのが今や通説である。それが「第3の使命」として法律に残っている。片や、ポスト・バーナンキ下のFRB、FOMCには、その「第3の使命」におそらく反する「金融システムの安定」を追及することが求められている。なんという皮肉、なんという矛盾だろうか。
「低い長期金利」という使命は、高金利にあえいでいた1970年代半ば、米国議会がFRB、FOMCに要求した名残だ。その後、ボルカー時代の金融引き締めによって高インフレが収まり、長期金利も低下し始めるにつれて、「低い長期金利」は、「デュアル・マンデートが達成できればついてくるオマケのようなもの」として考えられるようになったようだ。2007年4月、ミシュキンFRB理事(当時)は次のように語っている。「長期金利は、安定的な経済の下でのみ、低位で推移し続けることができる。このため(連銀法で掲げられた3つの)使命は、デュアル・マンデートと呼ばれるのです」。
現在のところ、「低い長期金利」という目立たない使命の見直しにかかわる議論は皆無だ。しかし、いずれ問題に気づく人が出てくるだろう。FRB、FOMCの金融政策は法律にのっとって運営されなければならない。「金融システムの安定」を金融政策の第3の使命と考えるのであれば、連銀法において、「低い長期金利」は「金融システムの安定」に一刻も早く書き換えられるべきなのである。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら



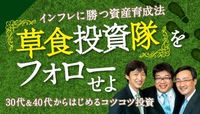
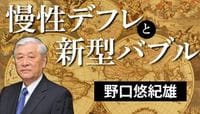


























無料会員登録はこちら
ログインはこちら