判断材料を与えるな!情報の非対称性下の鉄則
これら二つのルールは、一見するとどちらも同じように公平なルールであるように感じる。しかし、チェ教授らはここからさらに一歩分析を進め、情報の非対称性がある状況では、オークション方式の方がケーキカット方式よりも公平であることを明らかにした。
与えられたヤード数の下でのオフェンスの勝率は、各チームの戦術やコンディションなど、さまざまな要因に依存するものだ。そして、それらの要因に関する、自分のチームの私的情報は、各チーム十分に持っていることが多いと考えられる。
しかし相手チームについてはどうだろう。対戦相手の正確な情報は把握しにくいのではないだろうか。こういった情報の非対称性が存在する状況でケーキカット方式を用いると、次のような問題が発生してしまう。
先手は、後手の私的情報についてきちんと把握できないまま、自らの予想に基づいてヤード数を指定しなければならない。一方の後手は、先手の私的情報を直接観察することはできないものの、先手が提案したヤード数から間接的に、先手の私的情報の手掛かりを得ることができる。
結果的に、相手の情報を全く知らずに意思決定しなければならない先手と比べて、先手のヤード数を通じて両チームの情報を踏まえた意思決定のできる後手の方が有利になってしまうのだ。情報の非対称性がない状況では公平だったケーキカット方式にも、こういった弱点があったのである。
一方のオークション方式は、先手・後手といった非対称性がない対称的なルールなので、片方のチームが情報面で優位になることがない。そのため、上述したような情報の非対称性が存在したとしても、公平性が確保されるのだ。
チェ教授らのアイデアは、アメフトのOT問題を超えて、さまざまな分野に応用できる可能性がある。たとえば、将棋や囲碁などのボードゲームでも、先手・後手の有利・不利はよく議論されている。
ヤード数の代わりに、持ち時間などを入札単位とするオークション方式を採用することで、ひょっとするとこの場合にも、公平な対局が実現できるかもしれない。
【初出:2013.2.16「週刊東洋経済(シェール革命で日本は激変する)」】
(担当者通信欄)
「ケーキカット」方式、小さい頃、両親に知っておいて欲しかったです。姉弟でのケンカもこのルールの適用で随分と減ったのではないかと予想されます。怒りが生まれるのも、自分が損をしていると思うからこそのこと。しっかり納得できれば、無駄な衝突はなくなるのではないでしょうか。そして、相手の状況を推し量りながらも、どこまで譲歩できるかを提示させられてしまう「オークション」方式、こちらも提示する条件は自発的に決めたこと。そこで決まったことには従わざるをえません。こんな経済学の考え方を取り入れることが、「大人な振る舞い」を実現する助けになるのかもしれません。
さて、安田洋祐先生の「インセンティブの作法」最新記事は2013年3月11日(月)発売の「週刊東洋経済(特集は、1億人の税)」に掲載です!
【お金を使わず幸せに?物々交換の賢い仕組み】
東日本大震災から2年、あの震災直後の避難所で起こった支援物資の分配の問題を、経済学の観点から分析。どうすれば私たちは、より公平で効率的な決定を行えるのか?
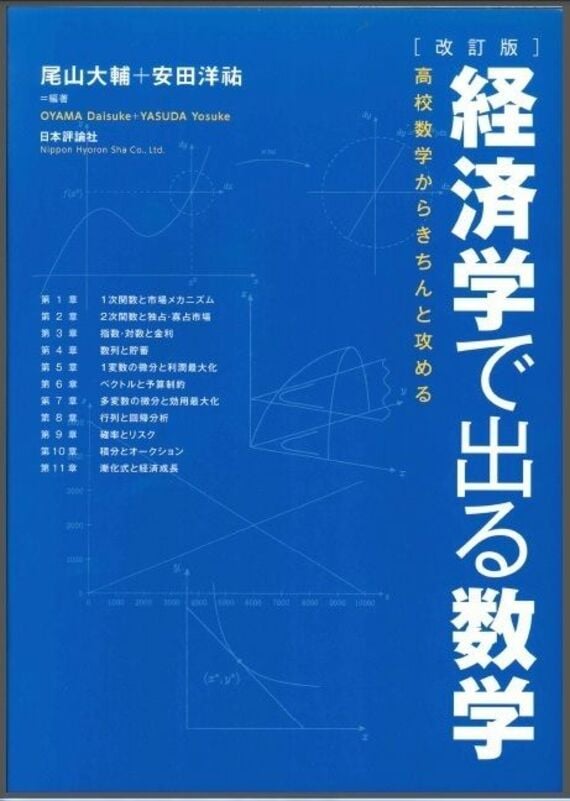
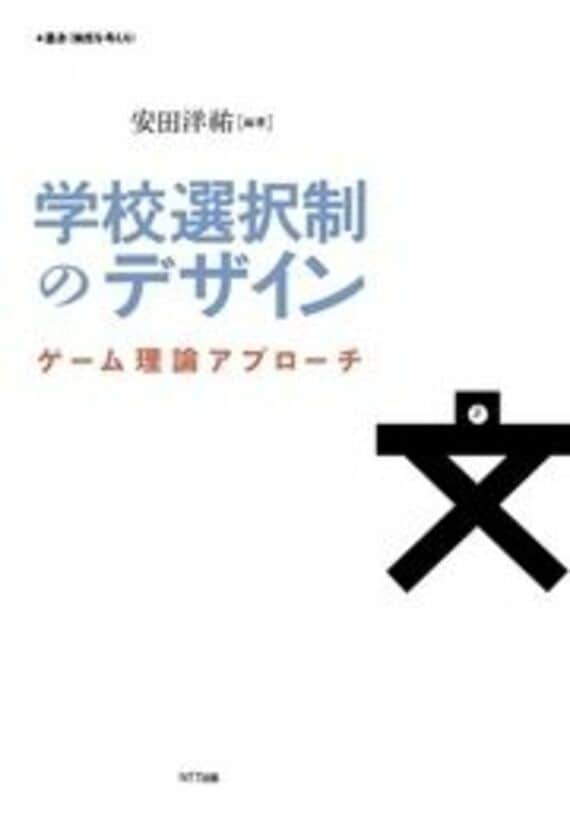
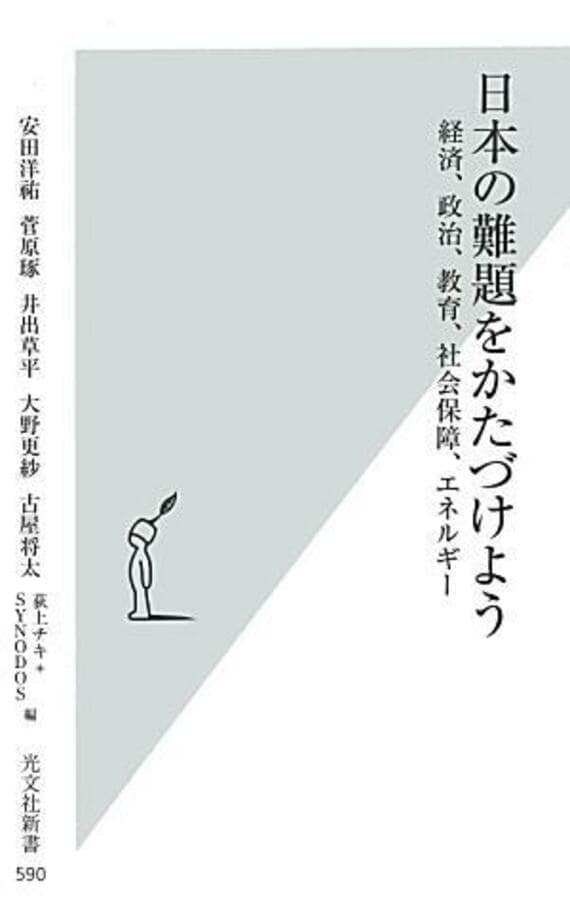
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら































無料会員登録はこちら
ログインはこちら