損傷を受けた脳は、いかに自己回復するのか 神経可塑性研究の最前線
そこでモスコヴィッツが行ったのは、神経科学の文献を読みあさり、慢性疼痛を解消する方法を自ら考えることであった。そして、その結果たどりついたのが、神経可塑性を利用するというアイデアである。
そもそも慢性疼痛はどのようにして生じるのだろう。ここで、「痛みのワインドアップ現象」という考えが参考になる。すなわち、たとえば身体の何らかの損傷により、激しい痛みが一定期間続くと、痛みと関連する脳のニューロンの結合が強化され、痛みの信号がいとも簡単に、しかも過剰なまでに検出されるようになってしまう、というのである。これはまさに「ニューロンの結合は変わりやすい」という事実によるものであり、その意味で、慢性疼痛は「可塑性の狂乱」だとも言える。
視覚活動によって痛みを圧倒する
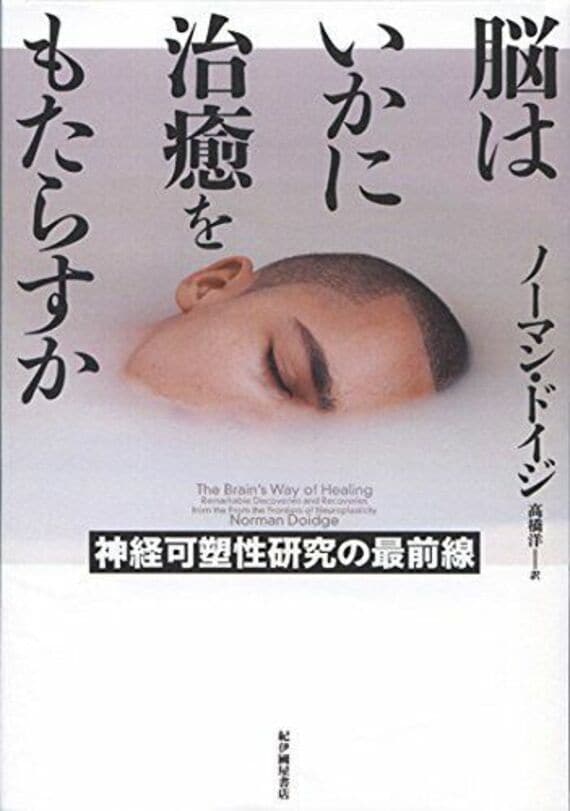
しかしそうだとしたら、そのようにして強化されたニューロンの結合を、これまた神経可塑性を利用して、穏やかなものにしてやることはできないだろうか。ふたつのニューロンが同時に発火を繰り返していると、それらの結合は強化される。反対に、それらのニューロンが繰り返し別々に発火していれば、両者の結びつきは弱くなる。つまり、脳の神経回路は「使わなければ失われる」のである。ならば、脳のなかに競合的な結合を新たに生み出してやることによって、慢性疼痛に関わる神経回路を弱めることもできるのではないか――とそうモスコヴィッツは考えたのである。
そして実際にモスコヴィッツが試みたのは、痛みが生じるまさにそのときに、特定の視覚化の作業を行うこと(具体的には、自身が描いた脳マップを思い浮かべること)であった。とりたてて「視覚化」であることにはそれなりの理由がある。というのも、視覚にはたくさんの脳領域が関与していて、とくにそのうちのいくつかの部位(後帯状皮質、後部頭頂葉)は痛みの処理とも関係しているからである。要するに、「視覚活動によって痛みを圧倒する」、「痛みに脳領域の使用権を明け渡さない」というのがここでの目論見であり、そしてその目論見は見事に成功する。痛みを感じたときに視覚化を実行するというその方法を徹底した結果、モスコヴィッツの慢性疼痛はなんと短期間で消失したのである。またそれのみならず、彼のもとを訪れる患者たちの多くも、同様の方法で実際に慢性疼痛を治癒させているという。
というのが、本書第1章で紹介されている「視覚化を用いた慢性疼痛の治療」の事例である。「そんな治療法があるのか」と驚かれる人も多いと思うが、驚くべき事例はそれだけにとどまらない。「歩くことでパーキンソン病の症状を抑え込む」という事例(第2章)から、「舌を刺激する装置(PoNS)で多発性硬化症を治療する」(第7章)、「特殊な聴覚トレーニングにより識字障害や自閉症を克服する」(第8章)といった事例まで、本書のエピソードにはまさに驚きが尽きない。それらの事例については、ぜひ驚きをもって本書自身に当たってほしいと思う。
ところで、おそらく本書の内容に対しては、驚嘆の念ばかりでなく、「そんな方法で本当に治るのか?」という疑念も寄せられることだろう。そうした疑念に応えるように、著者は随所で、それぞれの治療法の有効性を支持するような神経科学的知見に言及している。そのために本書は、けっしてただのエピソード集ではない、濃密かつ重厚なサイエンス書に仕上がっている。ただ、ないものねだりをひとつするならば、そういう内容の本であるからこそ、治療前後の変化を見てとれるような脳画像などを掲載してほしかったと思う。脳画像を含めた図版が極端に少なかった点が、本書を読んでいて少し残念に感じたところだ。
いずれにしても、刺激とフロンティア精神に満ちた好著であると思う。けっして医学のメインストリームではないそれぞれの治療法が、今後さらにどのような成果を残し、どう受け入れられていくのか。その近未来をぜひとも知りたいと思った。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

































無料会員登録はこちら
ログインはこちら