論語からケインズまで--「古典」が今おもしろい!
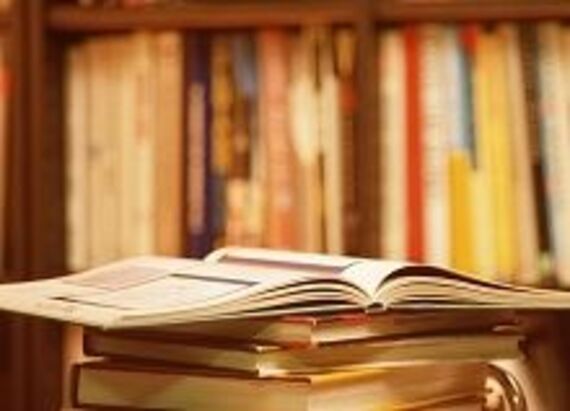
東京・神田神保町の三省堂書店本店。ここでちょっとした“異変”が起きている。『資本論』の著者、カール・マルクスの関連本が前年比4倍も売れているのだ。今年に入りマルクス関連本の新刊が相次いだことに加え、「雇用情勢が悪化したタイミングから急に売れ始めた」(売り場担当者)。
マルクス、アダム・スミス、ケインズ……。100年に一度といわれる経済危機の中で、経済学の分野では先哲が再び脚光を浴びている。
経済書だけではない。そのほかのジャンルでも、新刊の不振を尻目に、古典が堅調だ。岩波書店では全社の売り上げが下がりつつある中、古典タイトルの多い岩波文庫は横ばいを堅持。プラトン『ソクラテスの弁明』、夏目漱石『坊っちゃん』、ルソー『エミール』といった古典が根強い人気を誇る。
出版界は今、新訳ブームだ。きっかけは、2006年に発行された光文社古典新訳文庫『カラマーゾフの兄弟』。ロシアの文豪、ドストエフスキーの最後の長編小説である同書は、およそ30年ぶりに新訳が登場したことで、人気に火が付いた。全5冊の発行部数は100万部を突破。これまでドストエフスキーをあまり手にしなかった女性の購買も目立ち、古典の裾野を広げることに成功した。
新訳ブームは社会科学の分野にも及んでいる。アダム・スミス『国富論』(山岡洋一訳)、ケインズ『雇用、利子および貨幣の一般理論』(間宮陽介訳)などが、新訳によって生まれ変わった。新訳は古典にありがちな翻訳調の文体を排し、今の時代背景に合った読みやすい訳を追求する。古典はこれまでのような「気取った教養」ではなくなったのだ。
危機後の世界を古典から探る
古典に共通するのは、社会そして人間への深い洞察だ。たとえば近代経済学の祖スミスは、優れた道徳哲学の研究者だった。
資本主義の高度化は、世界に成長という果実をもたらした。だが、時に暴走し、バブルの崩壊、そして深刻な格差を引き起こす。そうした矛盾が、昨年来の世界同時不況で一気に表面化した。































