吉田茂 ポピュリズムに背を向けて 北康利著 ~破天荒なエピソードが促すリーダーシップ再考
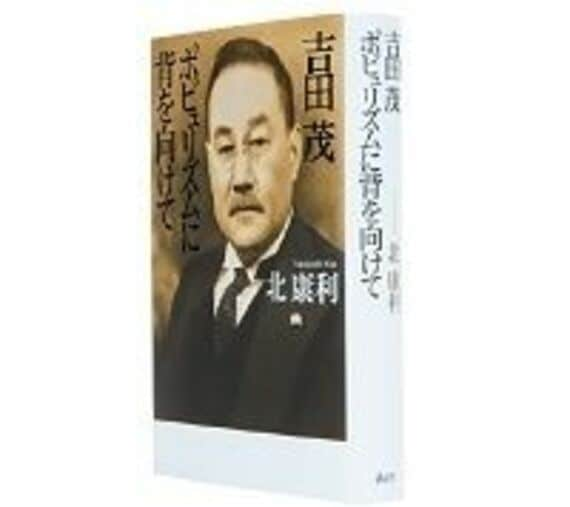
なかなかに痛快である。ほんの半世紀余り前のわが国にこんな指導者がいたとは。ワンマン宰相と呼ばれ、占領からの独立を果たし、「吉田ドクトリン」として知られるようになる戦後日本外交の枠組みを築き、そして池田勇人や佐藤栄作といった官僚派の後継人脈を生み出したことなどは、既によく知られている。しかしである。本書を通読すれば、吉田茂という人物の人を食ったようなユーモアのセンス、外交を見通す洞察力、時には生死をかけても実行する胆力、「武士は食わねど」を地で行くようなプライドの強さ、などを改めて思い知らされる。吉田の破天荒さを、満載のエピソードで語ったのが本書である。
1916年、首相に就任する寺内正毅から彼の秘書官を打診され、「私は首相なら務まると思いますが、首相秘書官は務まりません」と言ったそうである。こうした破天荒な外交官から政治家への人生を可能にしたものは何だったのか。
もちろん吉田の類稀なパーソナリティは極めて重要である。しかし同時に、国運を傾けた戦争や外交に明け暮れざるを得なかった時代背景も大きな要素であった。利益の分配や妥協による解決が政治の中心となった「55年体制期」の自民党政治とは異なる荒々しい権力政治と国際関係が、吉田の歩んだ時代の一貫した特質であった。
また、吉田を取り巻く人間関係にも色濃く現れているように、戦前の日本は今よりもはるかにエリート社会であった。何と言っても、岳父牧野伸顕の後ろ盾が陰に陽に大きな意味を持っていたことは明らかであろう。最後は牧野が何とか収拾してくれるに違いないという安心感があったかもしれない。また、第1次大戦後のパリ講和会議への随行をはじめ、牧野からは事あるごとに知恵と人脈、さらに機会を提供されてきた。
こうして、著者のいうポピュリズムに背を向けた真の政治リーダーが生み出された。51年のサンフランシスコ講和条約は、全力を傾けた吉田の努力なかりせば、実際よりもはるかに日本にとって厳しいものとなったに違いない。リーダーが自らの経験や知識の総力を挙げ、信念をもって難局に取り組んだ成果だったのである。
翻って、今日の世襲議員をめぐる議論の矮小さにはうんざりさせられる。しかし他方で、著者が強く批判する「大衆民主主義」と折り合いをつけることは今や避けて通れない。吉田の時代とは少しばかり違った政治の知恵が必要なのである。いずれにしても本書は、歴史的な総選挙を目前に控え、リーダーシップや民主主義の意味を考えるための格好の素材でもある。
きた・やすとし
作家。1960年名古屋市生まれ。東京大学法学部卒業後、富士銀行入行。富士証券投資戦略部長、みずほ証券財務開発部長、同業務企画部長等を歴任。2008年6月末でみずほ証券を退職し、本格的に作家活動に入る。著書に『白洲次郎』(山本七平賞受賞)など。
講談社 1890円 387ページ
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
































