「学校で習った英単語」なのにリスニングできない…。英語が苦手な人がハマっている"落とし穴"
この「モーラの等時性」こそが、日本語の大きな特徴です。どんなに長い単語でも、どんなに速く話しても、一つひとつの音の切れ目、つまり「拍」の長さが安定しているため、日本語はとても単調で平坦なリズム、フラットに聞こえます。
一方、英語は「Stress-timed language」と呼ばれ、強勢をつけてリズムを取る言語に分類されます。これは、単語や文のなかに「強く、長く、はっきりと発音される音(強勢音)」と、「弱く、短く、曖昧に発音される音(弱勢音)」があり、これらが交互に現れることで、リズムを形成する言語であることを意味します。
いわば、「メリハリが命」の言語です。そのため、英語を母国語とする話者はどうしても、「こんにちは」を「コニーチワ」のように、どこかを長く強く発声するような発音になりがちです。先ほど説明したように、リズムやメリハリが言語的に違うためです。

「情報伝達の効率化」がカギ
こうしたリズムやメリハリが「音声変化」に大きく関係しています。というのも、言語の究極の目標は、話者から聞き手へ、正確かつ効率的に情報を伝えること、つまり「情報伝達の効率化」です。
私たちがコミュニケーションをとるとき、脳は常に「いかにして少ない労力で多くの情報をやり取りするか」といった「最高のパフォーマンス」を追求しています。
発音する側にとっても、聞き取る側にとっても仮に、すべての単語、すべての音節を、同じ強さ、同じ長さで丁寧に発音しなければならないとしたら、大きな労力を伴います。
そのため、英語は、この「労力」を最適化するために、「重要な情報」と「そうでない情報」を音の強弱で明確に区別するという戦略を選びとりました。「大事なことは強く、大事でないことは弱く」発音するようになったのです。これが、英語がストレス(強勢)言語である本質的な理由です。




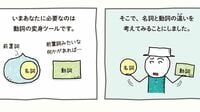


























無料会員登録はこちら
ログインはこちら