「亀のスープの作り方とは?」、朝ドラ「ばけばけ」で注目・小泉八雲がアメリカ時代にまとめた唯一の料理本がユニークすぎた
クレオールという語は多義的だが、その語源は「植民地生まれのヨーロッパ系住民」をあらわすスペイン語の「クリオーリョ」である。ニューオーリンズに赴いたハーンが見出したのは、ルイジアナ地方に入植したフランス人、スペイン人およびその子孫たちの文化だった。
ハーンは昔のフランス風ニューオーリンズの名残りの文化、つまり優美なフランス風の香りにアフリカ的な趣の混じった、この独特の文化を好んで街を探訪し、クレオール文化の衰退を憂えた。もともと寒さが苦手で、ラテン民族やラテン文化に深い共感を寄せるハーンには、この南欧的な雰囲気は大きな魅力だった。
クレオールの物語、音楽、ことわざ、薬草などと並んでクレオールの料理も、ハーンの知的好奇心を刺激したに違いない。クレオール文化への尽きぬ興味と食べることへの関心を重ね合わせたところに誕生したのが、生涯にただ一冊となった料理本『クレオール料理』(La Cuisine Créole)だった。
載っていない家庭料理はないほど詳しい
ハードカバーの分厚い本である。章立てだけを見ても、スープ、魚料理、肉料理、アントレ、野菜料理、卵料理、サラダとつけあわせ、ピクルス、パン、ラスク、ドーナツ、ワッフル、ケーキとお菓子、デザート、プディングとパイ、プリザーブ、シロップ、果実酒と飲み物、コーヒーにお茶、さらに病人や病後の人、虚弱体質の人向きのレシピまでカバーする念の入れ方だから、大部になるのも無理はない。
およそ家庭で作ろうとする食物でここに載っていないものがあろうか、と思うほどである。典型的なクレオール料理のザリガニスープ、ゴンボ、ジャンバラヤなどは言うまでもない。
スープやピクルスの章では、個々のレシピに入る前に調理器具その他について全般的な注意が述べられている。魚料理の章には亀のさばき方が、肉料理の章ならば各種の肉の調理法に加えてソースの作り方や盛りつけ方まで説明されているのである。
主婦が特別なメニューを記しておく料理ノートやカードとは異なり、この本では難易度に関わりなくレシピが並んでいる。できる限り多くを網羅するという方針で集められていることがわかる。
また、短い序文の中で、ハーンはこれが初のクレオール料理書であることを2回も述べている。そこには民俗学者としてのハーンに通じるもの、つまり記録にとどめておくこと自体にまず意義を認める姿勢が感じられる。
この本の記述の特徴の一つは、各料理の作り方が大変要領よく、手短に説明されていることである。ただ、材料とその分量を初めに書き抜くことはせず、作り方の手順を説明する文中に随時出すスタイルなので、必要な材料を前もってすばやく確かめるには不便を感じる。
また分量にしても、たとえば「よく太ったカニ六杯」といった具合におおざっぱなことがある。「よく太った」とはいったいどのくらいの大きさ、重さなのか――料理に不慣れな人ならとまどうかもしれない。
このような特徴が生まれたのは、ハーンがレシピを集めるにあたって友人たちの家庭で一つずつ料理を教わり、書き留めていったために相違ない。つまり、典型的な聞き書きのスタイルなのである。ベテランの主婦たちの説明を、ハーンはおそらくその場でメモしたのだろうと想像される。
民俗学者としてのハーンの側面は最近注目されているが、民話やことわざを収集したのと同じ動機、同じ要領で、ハーンはクレオール料理のレシピも集めたのだ。そう考えれば、ハーンが料理の本を著したのも、むしろ自然な成り行きだったのかもしれない。

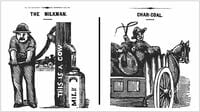





























無料会員登録はこちら
ログインはこちら