「公的年金があてにならない」って本当ですか?/分布推計が示す年金の構造的強さ
こうしたこともあり、今年6月23日の第21回全世代型社会保障構築会議でも、政治家や社会保障担当の官僚たちに対し、「政治・政策に関わる皆さんには、この国の年金制度が持つ構造的な強さに、もう少し自信を持っていただきたい」と、自然に発言することになる。
あの日の会議では、次のように話している。
残された課題とは何か
もちろん課題はある。
2018年頃から、勤労者には勤労者に相応しい被用者保険を保障することは「勤労者皆保険」と呼ばれていた。そして2022年12月にまとめられた全世代型社会保障構築会議の報告書は、「勤労者皆保険の実現に向けた取組」の工程として、 次の4つを挙げていた。
・常時5人以上を使用する個人事業所の非適用業種の解消
・ 週所定労働時間20時間未満の労働者、常時5人未満を使用する個人事業所への被用者保険の適用拡大
・ フリーランス・ギグワーカーの社会保険の適用の在り方の整理
これらはいずれも基礎年金の底上げに資する施策でもある。構築会議の報告書には、勤労者皆保険に向けて「被用者保険の適用拡大を更に進めていくにあたっては、マイナンバー制度を含め、デジタル技術の積極的な活用を図る」とも記されていた。勤労者皆保険はまだ道半ばにあり、実現に向けた改革の加速が求められている。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら



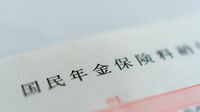



























無料会員登録はこちら
ログインはこちら