「公的年金があてにならない」って本当ですか?/分布推計が示す年金の構造的強さ
世の中では、「少子高齢化でモデル年金の所得代替率は下がる」という説明がなされている。そうであるのに、なぜ分布推計では、将来世代ほど給付水準が上がるのか。「ライフスタイルの変化が年金の未来を明るくする」では、その理由を「モデル年金」と「分布推計」の違いによって説明していたが、ここでは別の角度から簡潔に説明する。
賃金のサブシステムとしての社会保険
賃金は、病気、失業、引退という「支出の膨張」や「収入の途絶」を伴う生活リスクに対して脆弱である。さらに、親の介護や子育てといったライフイベントを契機とする支出増、収入減にも十分に対応できない。なぜなら賃金は、生きていくうえで生じる、そのような支出の膨張や収入の途絶に配慮して、増えたり支払われ続けたりすることはないからだ。そのため、生涯を通じた安定的な生活保障システムとして、賃金は不完全である。
これが、賃金システムが一般化する歴史の中で、多くの労働者は貧困リスクに直面してきた最大の理由である。
こうした課題に応える形で、日本を含む多くの国々は、賃金の欠陥を補う「サブシステム」として被用者保険を整備してきた。賃金と被用者保険という賃金のサブシステムを組み合わせた分配システムに変えることで、貧困に陥る人を減らす防貧機能、すなわちセーフティネットの強化を図ってきたのである。
誰もが高齢期に支出を膨張させる医療、介護などについては、若いときから保険料拠出の形で支出を前倒しで行うことにより、高齢期には保険給付の形で自己負担の支出を減らすことができる。社会保険は、生涯を通した「消費の平準化」(consumption smoothing)を実現させることによって、生活保障の機能をはたしているとも言える。
他方、日本では、男女平等や正規・非正規の格差是正を求める労働市場の改革、子育て・介護と仕事の両立支援、さらに厚生年金をはじめとする被用者保険の非正規雇用への適用拡大を、苦労しながらも進めてきた。並行して、さまざまな要因によって人々の意識も変化し、男女ともにライフスタイルは過去と比べて大きく様変わりしてきた。
このライフスタイルの変化は、より多くの人が賃金のサブシステムとしての被用者保険に自然に加入する社会への変化と結びつき、その結果、収入途絶や支出膨張といった生活リスクに対する社会全体での防貧機能が向上した。
そのことを、年金に関しては「分布推計」が、低年金者の減少という形で明らかにしたのである。対してこうした社会の変動は、モデル年金(夫が40年就業の専業主婦がいる世帯の年金額)には反映されない。拙稿「『さらばモデル年金』誰も知らない財政検証の進化」には、「モデル年金では女性はずっと専業主婦で3号のままです。モデル年金からは、今を生きる若い人たちが自分の将来を知ることができない」と書いている。



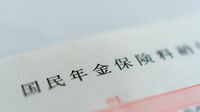



























無料会員登録はこちら
ログインはこちら