そのほかにも、例えば死んだ魚は、カニやヒトデ、オオグソクムシたちの良い餌になる。こうした海の“死体解体業者”は「スカベンジャー」と呼ばれ、自然界でも海底に沈んだ魚の死骸をきれいに食べてくれるのだ。
水槽に死んだ魚が落ちていたときも、いきなりスタッフに言うのではなく、ぐっとこらえて観察してみよう。カニやヒトデなんかが群がっていたら、餌として意図的に残されている可能性もあるからだ。
水族館で自然の摂理を知る
余談になるが、先ほどから述べているように、水族館は生きた生物を活餌として与えたり、瀕死または死亡した生き物をほかの生物の餌としたりすることが多い。
これを「残酷だ」などという輩とは、筆者は正直、口もききたくない。
そもそも人間が食う肉や魚だって、どこかで命を奪わなければならない。じゃ、完全なヴィーガンならいいかといえば、野菜や果物だって食われる時点である意味、命を失っている(だって、種はそのまま食うか、ゴミ箱に捨てているでしょ? あれも命の1つだよ)。
自然の摂理を知ることこそ、捕食者の責任であるならば、それをまざまざと見せてくれる水族館は、実にありがたい存在ではないか。
巡った水族館数が増えてくると、例外も数多く出てくるもの。先ほどのように、大水槽に小魚と大型の魚が混泳していながら、小魚が一切捕食されない水槽もある。
例えば、山梨県立富士湧水の里水族館(山梨県)では、ドーナツ型の水槽で、ヤマメなどの小魚と大きなニジマスが見事に共存している。また、京都水族館(京都府)では、チョウチョウウオなどの小魚が泳ぐ水槽の奥を、巨大なサメが通過していく光景が見られた。
ほかにも、いくつかの水族館でこんな水槽を見た。
「え? こんなのが同じ水槽にいたら、場合によっては捕食されるんじゃないの?」と思ったのだが、これが起き得ないのだ。理由は簡単。“同じ空間にいるように見えるだけ”だから。
実は、これらの水槽、小魚と大魚の水槽の間に、アクリルガラスの仕切りがあるのだ。これにより、小魚は小魚だけ、大魚は大魚だけで泳いでいるので、当然それを越えて捕食が起きることはないのである。
さすがにそのレベルの展示は多くはないが、大水槽でも工夫を凝らし、小魚が逃げ込めるような空洞をつくっている水族館もある。
大水槽の生物を維持するため、工夫を凝らすのが水族館の生き様だ。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

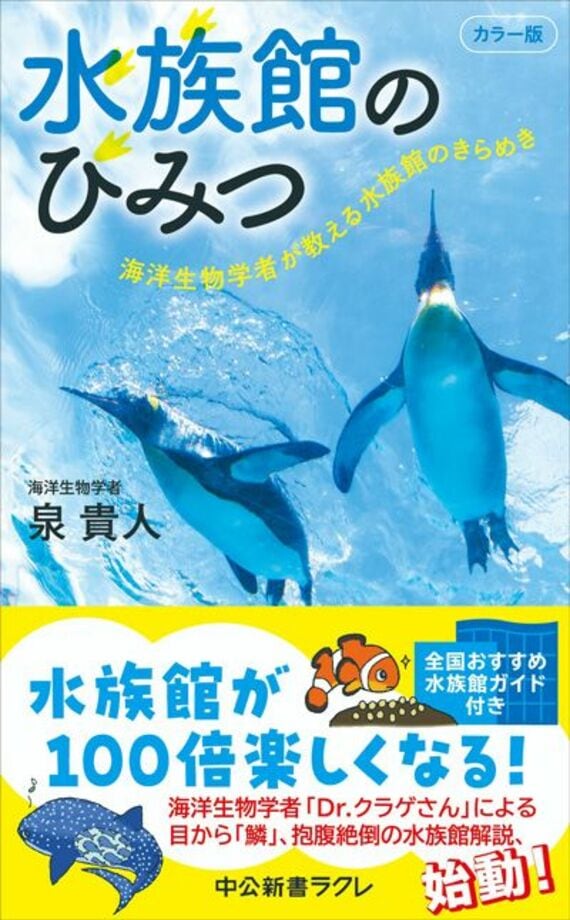






























無料会員登録はこちら
ログインはこちら