「世代で若者を論じることに意味がない」。そう断じる前に知ってほしい「一般化」の本当の意味
いっぽう利用率と異なる数値を示す指標がある。認知率である。上位からYouTube(98.2%)、Instagram(96.4%)、X(94.7%)、TikTok(94.2%)、Facebook(84.3%)、BeReal.(81.3%)と認知率は8割超えのSNSが6つ存在した。YouTubeを知らないZ世代が1.8%いるらしい。若者は多様である(知る/知らないだから二様と言うほうが正しい)。当たり前ながら利用している人に比べたら認知している人はかなり多い。
SNSの一般性は認知率からも説明できる。割合もさることながらSNSは社会に浸透しきったことで「ああまあ、そういうのあるよね」とハッキリ認知できるものになっている。たとえ自分が、そして若者全員がソレをしていなくても。
比率のみならず構造を見よ
一般性は別に「(ほぼ)全員が当てはまる傾向」だけを意味していない。「なるほど、それはあるわな」と納得感とリアリティを与えるかどうかもまた一般性の範疇なのだ。
その意味では既知であるかも問わない。「そういう話は知らなかったけど社会でそういうことが起きているのは想像に難くないね」と言えることもまた一般性なのである。
さらに重要なのは背景の「構造」を読み解くことである。最近の若者をめぐる言説について考えるとき、何割の若者に当てはまるかという個人特性のみならず、何がどのように若者を若者たらしめているのかについて考えるべきである。本書ではその「たらしめるもの」を構造と呼ぶ。
特異な若者が出現するとき、若者が突飛な言動をみせるとき、背後に必ずそうたらしめるものがある。それが構造であり、往々にして先行世代が築いたものである。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら

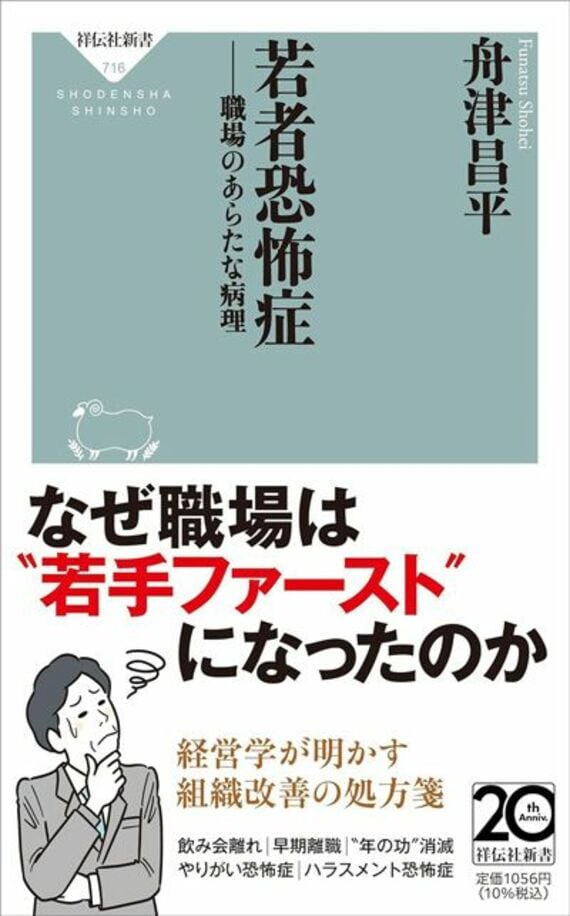






























無料会員登録はこちら
ログインはこちら